 鳥の中には、ヘリコプターのように空中でホバリングして静止できる種類がいます。
鳥の中には、ヘリコプターのように空中でホバリングして静止できる種類がいます。September 30, 2006
自分の行動を数値化してみる
空中でピタリと静止するため高速で羽ばたくので、ブーンとハチのような音がすることから英語ではハミングバードと呼ばれています。鳥の中では最も小さいグループで体重は2グラムから20グラム程度しかありません。北米から南米にかけて生息している鳥、そうハチドリです。
そのハチドリが主人公の話で、「ハチドリのひとしずく いま、私にできること」という本があります。南米はエクアドルの先住民に伝わる話だそうですが、昨年11月に本として出版される以前から、冊子になったり話題になるなどしていたので、内容をご存知の方も多いかも知れません。
この話を元に始まった「ハチドリ計画」のサイトをはじめ、あちこちでも紹介されていますが、参考までにストーリーを引用しておきます。
地球温暖化などの環境問題について、漠然とした問題意識は持っていても、自分一人の力はあまりに非力で、何をしようと無駄、全体へは、ほとんど影響を与えることもないと最初から諦めている人もいます。しかし、一人一人が小さな事からでも実践していくことこそが大切であることを、改めて気づかせてくれる話です。
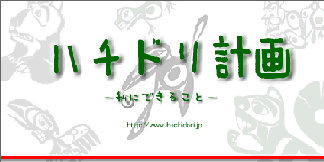 この物語の続きを描くのはあなたです、となっていますが、一人の小さな力も、集まれば大きなムーブメントになること、大きなムーブメントも、始まりは小さな一人の行動からだと思えるようになるかも知れません。自分には何も出来ないと考えるのではなく、出来ることから始めてみようと肩の力が抜けたりします。
この物語の続きを描くのはあなたです、となっていますが、一人の小さな力も、集まれば大きなムーブメントになること、大きなムーブメントも、始まりは小さな一人の行動からだと思えるようになるかも知れません。自分には何も出来ないと考えるのではなく、出来ることから始めてみようと肩の力が抜けたりします。
シンプルなストーリーですが、人々の心に響くものがあります。小さな事でもいい、自分の出来ることをすればいいわけです。しかし、始めてみると、それがどのくらいの効果を持つものなのか知りたくなる人もいるでしょう。そんな人も納得出来る物差しが用意されています。
この本やハチドリ計画のサイトには、一人一人に出来ることが紹介されていますが、同時に「ポトリ」という単位が提案されています。ハチドリが落とす水の雫の音の「ポトリ」からきているそうですが、地球温暖化の主原因となっている二酸化炭素の排出を100グラム減らすと1ポトリです。
ふだんの生活で考えると、シャワーを使う時間を1分短縮すると0.6ポトリ、冷蔵庫のモノの詰め込みすぎをやめると1日で0.7ポトリ、炊飯ジャーの保温をやめると一日0.8ポトリなどとなっています。小さな行動でも数字に表すと実感が沸きます。
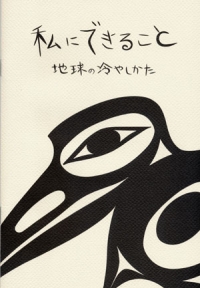 フードマイレージという考え方も紹介されています。食べ物が生産された場所から消費される場所まで運ばれる距離のことで、輸送で排出されるCO2の量が距離から計算出来るわけです。地元の産品を選択すれば、このフードマイレージを少なくすることができます。
フードマイレージという考え方も紹介されています。食べ物が生産された場所から消費される場所まで運ばれる距離のことで、輸送で排出されるCO2の量が距離から計算出来るわけです。地元の産品を選択すれば、このフードマイレージを少なくすることができます。
オーストラリア産のアスパラガスを国産のものにすると4.1ポトリ、アメリカ産のイチゴ5個で6.2ポトリなどとなります。自分に出来ることを効果的に積み重ねて行くことも出来ますし、数字をカウントすることで、より楽しく感じられるかも知れません。
冷暖房の設定温度とか、スイッチをこまめに切るなど以外に、サイトでは取り上げられていませんが、自転車を使うというのも当然あります。私などは趣味でもあるので、環境を考えた行動とは言えない部分もありますが(笑)、それでも意識して、クルマに乗るところをあえて自転車にする場合もあるわけです。
そこで自転車に乗ると何ポトリくらいになるのか調べてみました。今までクルマを使っていた買い物とか通勤、保育園の送迎などをクルマから自転車に変更したとします。乗っている車種にもよりますが、1キロ当り2ポトリ程度にもなります。例えば2キロの距離を朝夕送迎すれば8キロ、16ポトリです。
調べてみると、車種によってCO2排出量はずい分違います。日本自動車工業会のサイトから、メーカー名をクリックし、一度お使いの車種の排出量を調べてみてもいいでしょう。大型のセダンなどだと1キロ当り3ポトリ、ファミリーカーで2ポトリ、軽自動車なら1ポトリ程度でしょうか。いずれにせよ、不必要なクルマの利用を減らす効果は小さくありません。
一方で、環境省の調べによれば日本の2004年度のCO2総排出量は12億8600万トンです。京都議定書の基準年、1990年と比較すると、12.4%増加しています。もちろん割合で言えば、我々の生活以外の部分、産業や発電、運輸などの部門からも多く排出されています。
 しかし、我々の消費する分を生産したり運んだりしていると考えれば、結局のところ直接間接に我々が排出していることになります。そう考えると国民一人当たり実に10.07トンも排出し、8.8%増加しています。基準年から6%の削減義務とあわせると、現状から約14%削減しなければなりません。
しかし、我々の消費する分を生産したり運んだりしていると考えれば、結局のところ直接間接に我々が排出していることになります。そう考えると国民一人当たり実に10.07トンも排出し、8.8%増加しています。基準年から6%の削減義務とあわせると、現状から約14%削減しなければなりません。
10トンの14%と考えると、一人1日あたりに換算して38ポトリ減らさなければなりません。お年寄りから赤ん坊まで含めてですので、仮に15歳から64歳までで削減するとなると、59ポトリ必要になります。
自転車だけで実現させるわけではありませんが、キロ数で言うと1日約30キロです。毎日30キロ自転車で走るのは可能ですが、削減のためにはクルマを使う分を自転車にしなければならないので、毎日それだけクルマを使っている人でなければ削減できません。
やはり容易な数字ではないようです。ここまで考えてしまうと、ハチドリの「出来ることをする」という考え方からは外れてしまいそうですが、せっかくやるなら、出来る範囲で「出来ること」を効果的に積み重ねたい気もします。
実際には、森林による吸収とか、新技術の開発、排出権取引などもありますし、必ずしも悲観するものではありません。もちろん、一人一人の出来ることも自転車や節電、食べ物だけとも限りません。中には、出来るのに、気づかず見逃していることもありそうです。身近に転がっているポトリを、もっと捜してみることも必要かも知れません。
ちなみに数字を調べていて思ったのですが、政府もマイナス6%などのキャンペーンで国民にアイドリングストップを勧めるのもいいですが、まず隗より始めよです。公用車を自転車にしろとは言いませんが、軽自動車を黒く塗ったのではダメでしょうかね(笑)。
関連記事
騙されて買わされる無駄な物
省エネ型家電に買い換えれば効果も持続しそうだが注意も必要
そんな店から買わないよ
政府も温暖化防止を訴え、チーム・マイナス6%を展開中
本当の意味で優しいのは誰か
エコで環境に優しいと言うのも疑ってみる必要がありそう
そのハチドリが主人公の話で、「ハチドリのひとしずく いま、私にできること」という本があります。南米はエクアドルの先住民に伝わる話だそうですが、昨年11月に本として出版される以前から、冊子になったり話題になるなどしていたので、内容をご存知の方も多いかも知れません。
この話を元に始まった「ハチドリ計画」のサイトをはじめ、あちこちでも紹介されていますが、参考までにストーリーを引用しておきます。
南アメリカの先住民に伝わるハチドリの物語
あるとき森が燃えていました
森の生きものたちは
われ先にと逃げていきました
でもクリキンディという名のハチドリだけは
いったりきたり
口ばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは
火の上に落としていきます
動物たちがそれを見て
「そんなことをしていったい何になるんだ」
といって笑います
クリキンディはこう答えました
「私は私にできることをしているの」
地球温暖化などの環境問題について、漠然とした問題意識は持っていても、自分一人の力はあまりに非力で、何をしようと無駄、全体へは、ほとんど影響を与えることもないと最初から諦めている人もいます。しかし、一人一人が小さな事からでも実践していくことこそが大切であることを、改めて気づかせてくれる話です。
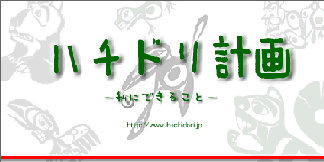 この物語の続きを描くのはあなたです、となっていますが、一人の小さな力も、集まれば大きなムーブメントになること、大きなムーブメントも、始まりは小さな一人の行動からだと思えるようになるかも知れません。自分には何も出来ないと考えるのではなく、出来ることから始めてみようと肩の力が抜けたりします。
この物語の続きを描くのはあなたです、となっていますが、一人の小さな力も、集まれば大きなムーブメントになること、大きなムーブメントも、始まりは小さな一人の行動からだと思えるようになるかも知れません。自分には何も出来ないと考えるのではなく、出来ることから始めてみようと肩の力が抜けたりします。シンプルなストーリーですが、人々の心に響くものがあります。小さな事でもいい、自分の出来ることをすればいいわけです。しかし、始めてみると、それがどのくらいの効果を持つものなのか知りたくなる人もいるでしょう。そんな人も納得出来る物差しが用意されています。
この本やハチドリ計画のサイトには、一人一人に出来ることが紹介されていますが、同時に「ポトリ」という単位が提案されています。ハチドリが落とす水の雫の音の「ポトリ」からきているそうですが、地球温暖化の主原因となっている二酸化炭素の排出を100グラム減らすと1ポトリです。
ふだんの生活で考えると、シャワーを使う時間を1分短縮すると0.6ポトリ、冷蔵庫のモノの詰め込みすぎをやめると1日で0.7ポトリ、炊飯ジャーの保温をやめると一日0.8ポトリなどとなっています。小さな行動でも数字に表すと実感が沸きます。
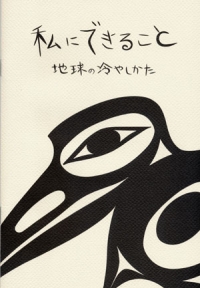 フードマイレージという考え方も紹介されています。食べ物が生産された場所から消費される場所まで運ばれる距離のことで、輸送で排出されるCO2の量が距離から計算出来るわけです。地元の産品を選択すれば、このフードマイレージを少なくすることができます。
フードマイレージという考え方も紹介されています。食べ物が生産された場所から消費される場所まで運ばれる距離のことで、輸送で排出されるCO2の量が距離から計算出来るわけです。地元の産品を選択すれば、このフードマイレージを少なくすることができます。オーストラリア産のアスパラガスを国産のものにすると4.1ポトリ、アメリカ産のイチゴ5個で6.2ポトリなどとなります。自分に出来ることを効果的に積み重ねて行くことも出来ますし、数字をカウントすることで、より楽しく感じられるかも知れません。
冷暖房の設定温度とか、スイッチをこまめに切るなど以外に、サイトでは取り上げられていませんが、自転車を使うというのも当然あります。私などは趣味でもあるので、環境を考えた行動とは言えない部分もありますが(笑)、それでも意識して、クルマに乗るところをあえて自転車にする場合もあるわけです。
そこで自転車に乗ると何ポトリくらいになるのか調べてみました。今までクルマを使っていた買い物とか通勤、保育園の送迎などをクルマから自転車に変更したとします。乗っている車種にもよりますが、1キロ当り2ポトリ程度にもなります。例えば2キロの距離を朝夕送迎すれば8キロ、16ポトリです。
調べてみると、車種によってCO2排出量はずい分違います。日本自動車工業会のサイトから、メーカー名をクリックし、一度お使いの車種の排出量を調べてみてもいいでしょう。大型のセダンなどだと1キロ当り3ポトリ、ファミリーカーで2ポトリ、軽自動車なら1ポトリ程度でしょうか。いずれにせよ、不必要なクルマの利用を減らす効果は小さくありません。
一方で、環境省の調べによれば日本の2004年度のCO2総排出量は12億8600万トンです。京都議定書の基準年、1990年と比較すると、12.4%増加しています。もちろん割合で言えば、我々の生活以外の部分、産業や発電、運輸などの部門からも多く排出されています。
 しかし、我々の消費する分を生産したり運んだりしていると考えれば、結局のところ直接間接に我々が排出していることになります。そう考えると国民一人当たり実に10.07トンも排出し、8.8%増加しています。基準年から6%の削減義務とあわせると、現状から約14%削減しなければなりません。
しかし、我々の消費する分を生産したり運んだりしていると考えれば、結局のところ直接間接に我々が排出していることになります。そう考えると国民一人当たり実に10.07トンも排出し、8.8%増加しています。基準年から6%の削減義務とあわせると、現状から約14%削減しなければなりません。10トンの14%と考えると、一人1日あたりに換算して38ポトリ減らさなければなりません。お年寄りから赤ん坊まで含めてですので、仮に15歳から64歳までで削減するとなると、59ポトリ必要になります。
自転車だけで実現させるわけではありませんが、キロ数で言うと1日約30キロです。毎日30キロ自転車で走るのは可能ですが、削減のためにはクルマを使う分を自転車にしなければならないので、毎日それだけクルマを使っている人でなければ削減できません。
やはり容易な数字ではないようです。ここまで考えてしまうと、ハチドリの「出来ることをする」という考え方からは外れてしまいそうですが、せっかくやるなら、出来る範囲で「出来ること」を効果的に積み重ねたい気もします。
実際には、森林による吸収とか、新技術の開発、排出権取引などもありますし、必ずしも悲観するものではありません。もちろん、一人一人の出来ることも自転車や節電、食べ物だけとも限りません。中には、出来るのに、気づかず見逃していることもありそうです。身近に転がっているポトリを、もっと捜してみることも必要かも知れません。
ちなみに数字を調べていて思ったのですが、政府もマイナス6%などのキャンペーンで国民にアイドリングストップを勧めるのもいいですが、まず隗より始めよです。公用車を自転車にしろとは言いませんが、軽自動車を黒く塗ったのではダメでしょうかね(笑)。
関連記事
騙されて買わされる無駄な物
省エネ型家電に買い換えれば効果も持続しそうだが注意も必要
そんな店から買わないよ
政府も温暖化防止を訴え、チーム・マイナス6%を展開中
本当の意味で優しいのは誰か
エコで環境に優しいと言うのも疑ってみる必要がありそう

Amazonの自転車関連グッズ
Amazonで自転車関連のグッズを見たり注文することが出来ます。

Posted by cycleroad at 19:00│Comments(0)│TrackBack(0)
この記事へのトラックバックURL
※全角800字を越える場合は2回以上に分けて下さい。(書込ボタンを押す前に念のためコピーを)