 今から20年後は、どんな社会になっているのでしょうか。
今から20年後は、どんな社会になっているのでしょうか。March 02, 2007
イノベーションが必要なもの
安倍内閣の政策ビジョンとも言うべき、イノベーションによる成長戦略を描いた「イノベーション25戦略会議」の中間取りまとめ案が先月末発表されました。2025年に実現を目指す社会への提言として、将来実現が期待される技術の例が紹介されています。
 その中には、カプセル一錠で寝ながら健康診断、東京・大阪間を50分で結ぶ、一家に一台家庭ロボットで家事から解放、がん・心筋梗塞・脳卒中を克服、高齢者でも丈夫な体で認知症も激減、200平米200年住宅、ヘッドホン一つであらゆる国の人とコミュニケーション、など魅力的な未来が並びます。
その中には、カプセル一錠で寝ながら健康診断、東京・大阪間を50分で結ぶ、一家に一台家庭ロボットで家事から解放、がん・心筋梗塞・脳卒中を克服、高齢者でも丈夫な体で認知症も激減、200平米200年住宅、ヘッドホン一つであらゆる国の人とコミュニケーション、など魅力的な未来が並びます。
他にも、走れば走るほど空気を綺麗にする自動車、不毛の砂漠に緑のオアシス、家に居ながらサイバーワールド上で日本や世界を体験、衝突できない車、センサーネットワークで守る子どもの安全、ロボットが月旅行など、さまざまな技術が示されています。
これを見て感じることは人それぞれだと思います。魅力的な未来図であることは間違いありません。ただ、戦後の高度経済成長の時代なら、素直にバラ色の未来が信じられたかも知れませんが、今の時代、夢のような未来を単純に受け入れられないのは私だけではないと思います。
単なる未来予想ではなく、なるべく科学的な知見や技術的裏づけを元に書かれているようですから、理論的、技術的に不可能ではないでしょう。しかし、技術的に可能であっても実現しないものはいくらでもあります。経済原理や社会的な制約をはじめ、実現に不可欠な条件はいくつもあるわけです。
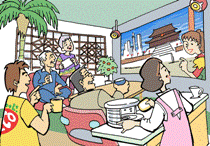 そもそも、地球規模で経済の持続可能性を揺るがすような状況があります。エネルギーや資源の獲得は今後ますます困難になっていくでしょうし、地球温暖化や気候変動の問題、人口の爆発的増加、水や食料の深刻な不足、テロや国際紛争、どれ一つとっても困難な問題です。
そもそも、地球規模で経済の持続可能性を揺るがすような状況があります。エネルギーや資源の獲得は今後ますます困難になっていくでしょうし、地球温暖化や気候変動の問題、人口の爆発的増加、水や食料の深刻な不足、テロや国際紛争、どれ一つとっても困難な問題です。
例えば空気中の二酸化炭素をエネルギー源とするクルマなど、こうした大きな課題を根本的に解決するような革新的イノベーションの出現は切に期待しますが、そう簡単なことではないでしょう。豊富な資源やエネルギーを使い、環境への影響を気にせずに技術革新に邁進出来る時代でないことは間違いありません。
有名な「イノベーションのジレンマ」に陥ってしまうことも考えられます。顧客の意見に熱心に耳を傾け、新技術への投資を積極的に行い、常に高品質の製品やサービスを提供している業界トップの優良企業ほど、その優れた経営のために失敗を招き、トップの地位を失ってしまうというものです。

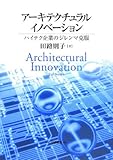 優良企業が顧客のニーズに応えて、より高機能な商品の開発に力を入れ、イノベーションを持続していくと、いつしか技術革新のレベルが顧客のニーズや活用能力を超えてしまい、行き過ぎてしまう。そこに現れた新興企業の、より安くて単純、高すぎる機能が不要な多くの顧客に十分な性能の製品に負けてしまうわけです。
優良企業が顧客のニーズに応えて、より高機能な商品の開発に力を入れ、イノベーションを持続していくと、いつしか技術革新のレベルが顧客のニーズや活用能力を超えてしまい、行き過ぎてしまう。そこに現れた新興企業の、より安くて単純、高すぎる機能が不要な多くの顧客に十分な性能の製品に負けてしまうわけです。
こうした例は過去にも多いですし、国家をあげて奨励するイノベーションによる新製品が、非常に魅力的であるにもかかわらず、顧客に受け入れられない場合もあるわけです。日本だけの独自規格にならざるを得なかったり、それがまた、その後の開発の阻害要因になってしまうことも少なくありません。
特に環境への意識が世界的に高まっている昨今、今までより便利、速い、手間が省ける、といった価値観だけで、よりコストが高かったり、環境への負担が高かったりするシステムが世界に受け入れられるとは限りません。夢の技術を示されても、その実現を無条件に期待出来ないわけです。
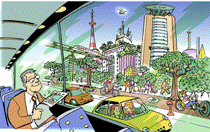 政治が、こうした国家の長期的ビジョンを示すことは重要だと思います。社会の閉塞感を払拭して欲しいと期待する向きもあるでしょう。もちろんグローバル化の時代に、中国やインドなどについて語るまでもなく、日本の従来型の成功モデルだけでは、今後やっていけないのも間違いありません。
政治が、こうした国家の長期的ビジョンを示すことは重要だと思います。社会の閉塞感を払拭して欲しいと期待する向きもあるでしょう。もちろんグローバル化の時代に、中国やインドなどについて語るまでもなく、日本の従来型の成功モデルだけでは、今後やっていけないのも間違いありません。
イノベーションは単なる「技術」の革新だけではなく、社会の仕組みや国民の生活を含めて従来の慣習を打ち破ることによって大いなる進歩をもたらし、新たな価値や市場を創造し、今後の経済を支えていく死活的に重要な要素であることも確かでしょう。
こうしたイノベーションを具体化するため、中間取りまとめでは次世代を担う若い人材への投資や、イノベーションの主要な発信地となる大学の改革などを提言しています。しかし、イノベーションが進んでも、それが社会に反映していくには別の要素も関わってきます。
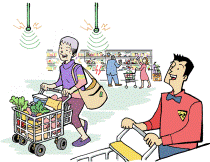 国家戦略を、それだけで論じるつもりはありませんが、自転車ブログなので、自転車の例を挙げてみましょう。中間取りまとめでは、わかりやすく示すために、「伊野辺(イノベ)家の一日」というストーリー仕立てで具体例を紹介しています。
国家戦略を、それだけで論じるつもりはありませんが、自転車ブログなので、自転車の例を挙げてみましょう。中間取りまとめでは、わかりやすく示すために、「伊野辺(イノベ)家の一日」というストーリー仕立てで具体例を紹介しています。
内容はリンク先の首相官邸のホームページをみていただくとして、その中に次のような一節が出てきます。
ここで言う電気自転車がどのようなものかはわかりません。でも電気だけで動くなら、それは自転車ではなく電動オートバイです。健康にいいと書かれていますので、自分の足でもペダルをこぐ電動アシスト自転車のようです。そくて電動アシスト自転車なら、言うまでもなく既に普及しています。
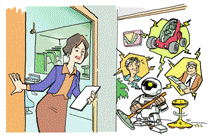 電動アシスト自転車は、電動オートバイにならないよう、むしろ法令で出力が抑えられているくらいで、既に充分な機能を持っています。電池の容量には多少改善の余地があるかも知れませんが、これ以上進化したら、電気オートバイにするしかありません。
電動アシスト自転車は、電動オートバイにならないよう、むしろ法令で出力が抑えられているくらいで、既に充分な機能を持っています。電池の容量には多少改善の余地があるかも知れませんが、これ以上進化したら、電気オートバイにするしかありません。
つまり自転車専用レーンが作られていないだけで、この部分だけは2025年を待たずに実現可能なわけです。これがあるべき未来の姿ならば、必要なのはイノベーションではなく政治です。この例のみでは決めつけられませんが、技術や科学が進歩しても、政治や行政が変わらなければ実現しないことも多そうです。
自転車を未来の乗り物だと言うつもりはありませんが、有機的に機能する都市交通システム全体としてなら、充分イノベーションとなりうる存在です。それこそ、技術の粋を集めて作った次世代型の省エネ高機能タイプの高価格なクルマがそっぽを向かれ、人々は自転車を選択するかも知れません。
イノベーションを否定するものではありませんが、夢のような未来の予想図が、なんとなく空々しく感じられるのは、政治に期待できないことにも原因がありそうです。談合や天下り、利権や既得権にまみれた政官財の癒着や、政治や行政の仕組みにもイノベーションの必要がありそうです。
政府がまとめて、イノベ家(笑)の一日なんてやられると陳腐に見えてしまいますが、それぞれの技術はすごいものが多いですし、期待したいものもたくさんあります。ワクワクするような未来が本当に実現するような社会になって欲しいものですね。
関連記事
ベロシティという都市の理想
実現の可能性はともかく、夢のような自転車未来都市構想がある
ふだん使わないものを生かす
こんな突飛な空想が現実になることも、ないとは言えないだろう
夢から覚めた現実的未来都市
交通の未来を担うのは、こんな自転車輸送システムかも知れない
 その中には、カプセル一錠で寝ながら健康診断、東京・大阪間を50分で結ぶ、一家に一台家庭ロボットで家事から解放、がん・心筋梗塞・脳卒中を克服、高齢者でも丈夫な体で認知症も激減、200平米200年住宅、ヘッドホン一つであらゆる国の人とコミュニケーション、など魅力的な未来が並びます。
その中には、カプセル一錠で寝ながら健康診断、東京・大阪間を50分で結ぶ、一家に一台家庭ロボットで家事から解放、がん・心筋梗塞・脳卒中を克服、高齢者でも丈夫な体で認知症も激減、200平米200年住宅、ヘッドホン一つであらゆる国の人とコミュニケーション、など魅力的な未来が並びます。他にも、走れば走るほど空気を綺麗にする自動車、不毛の砂漠に緑のオアシス、家に居ながらサイバーワールド上で日本や世界を体験、衝突できない車、センサーネットワークで守る子どもの安全、ロボットが月旅行など、さまざまな技術が示されています。
これを見て感じることは人それぞれだと思います。魅力的な未来図であることは間違いありません。ただ、戦後の高度経済成長の時代なら、素直にバラ色の未来が信じられたかも知れませんが、今の時代、夢のような未来を単純に受け入れられないのは私だけではないと思います。
単なる未来予想ではなく、なるべく科学的な知見や技術的裏づけを元に書かれているようですから、理論的、技術的に不可能ではないでしょう。しかし、技術的に可能であっても実現しないものはいくらでもあります。経済原理や社会的な制約をはじめ、実現に不可欠な条件はいくつもあるわけです。
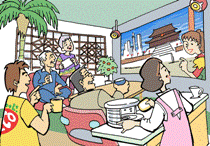 そもそも、地球規模で経済の持続可能性を揺るがすような状況があります。エネルギーや資源の獲得は今後ますます困難になっていくでしょうし、地球温暖化や気候変動の問題、人口の爆発的増加、水や食料の深刻な不足、テロや国際紛争、どれ一つとっても困難な問題です。
そもそも、地球規模で経済の持続可能性を揺るがすような状況があります。エネルギーや資源の獲得は今後ますます困難になっていくでしょうし、地球温暖化や気候変動の問題、人口の爆発的増加、水や食料の深刻な不足、テロや国際紛争、どれ一つとっても困難な問題です。例えば空気中の二酸化炭素をエネルギー源とするクルマなど、こうした大きな課題を根本的に解決するような革新的イノベーションの出現は切に期待しますが、そう簡単なことではないでしょう。豊富な資源やエネルギーを使い、環境への影響を気にせずに技術革新に邁進出来る時代でないことは間違いありません。
有名な「イノベーションのジレンマ」に陥ってしまうことも考えられます。顧客の意見に熱心に耳を傾け、新技術への投資を積極的に行い、常に高品質の製品やサービスを提供している業界トップの優良企業ほど、その優れた経営のために失敗を招き、トップの地位を失ってしまうというものです。

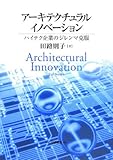 優良企業が顧客のニーズに応えて、より高機能な商品の開発に力を入れ、イノベーションを持続していくと、いつしか技術革新のレベルが顧客のニーズや活用能力を超えてしまい、行き過ぎてしまう。そこに現れた新興企業の、より安くて単純、高すぎる機能が不要な多くの顧客に十分な性能の製品に負けてしまうわけです。
優良企業が顧客のニーズに応えて、より高機能な商品の開発に力を入れ、イノベーションを持続していくと、いつしか技術革新のレベルが顧客のニーズや活用能力を超えてしまい、行き過ぎてしまう。そこに現れた新興企業の、より安くて単純、高すぎる機能が不要な多くの顧客に十分な性能の製品に負けてしまうわけです。こうした例は過去にも多いですし、国家をあげて奨励するイノベーションによる新製品が、非常に魅力的であるにもかかわらず、顧客に受け入れられない場合もあるわけです。日本だけの独自規格にならざるを得なかったり、それがまた、その後の開発の阻害要因になってしまうことも少なくありません。
特に環境への意識が世界的に高まっている昨今、今までより便利、速い、手間が省ける、といった価値観だけで、よりコストが高かったり、環境への負担が高かったりするシステムが世界に受け入れられるとは限りません。夢の技術を示されても、その実現を無条件に期待出来ないわけです。
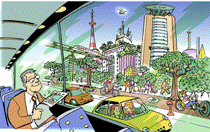 政治が、こうした国家の長期的ビジョンを示すことは重要だと思います。社会の閉塞感を払拭して欲しいと期待する向きもあるでしょう。もちろんグローバル化の時代に、中国やインドなどについて語るまでもなく、日本の従来型の成功モデルだけでは、今後やっていけないのも間違いありません。
政治が、こうした国家の長期的ビジョンを示すことは重要だと思います。社会の閉塞感を払拭して欲しいと期待する向きもあるでしょう。もちろんグローバル化の時代に、中国やインドなどについて語るまでもなく、日本の従来型の成功モデルだけでは、今後やっていけないのも間違いありません。イノベーションは単なる「技術」の革新だけではなく、社会の仕組みや国民の生活を含めて従来の慣習を打ち破ることによって大いなる進歩をもたらし、新たな価値や市場を創造し、今後の経済を支えていく死活的に重要な要素であることも確かでしょう。
こうしたイノベーションを具体化するため、中間取りまとめでは次世代を担う若い人材への投資や、イノベーションの主要な発信地となる大学の改革などを提言しています。しかし、イノベーションが進んでも、それが社会に反映していくには別の要素も関わってきます。
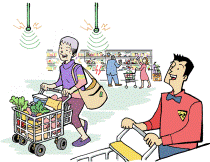 国家戦略を、それだけで論じるつもりはありませんが、自転車ブログなので、自転車の例を挙げてみましょう。中間取りまとめでは、わかりやすく示すために、「伊野辺(イノベ)家の一日」というストーリー仕立てで具体例を紹介しています。
国家戦略を、それだけで論じるつもりはありませんが、自転車ブログなので、自転車の例を挙げてみましょう。中間取りまとめでは、わかりやすく示すために、「伊野辺(イノベ)家の一日」というストーリー仕立てで具体例を紹介しています。内容はリンク先の首相官邸のホームページをみていただくとして、その中に次のような一節が出てきます。
祖父の一郎が、電気自転車で出勤。
電池技術の進歩で電気自転車の機能が進化したことと、自転車専用レーンが作られたことで、自転車通勤は大ブームになっている。地球にやさしく、健康にいいのが人気の秘密だと言われている。
「20年前に比べて、格段に排気ガスが減り、沿道に緑が多いので、まるでサイクリングを楽しんでいるようだ」と、一郎は通勤しながら感じるのだった。自宅から10キロ圏内ならば、一郎の年齢でも楽々通勤可能である。
ここで言う電気自転車がどのようなものかはわかりません。でも電気だけで動くなら、それは自転車ではなく電動オートバイです。健康にいいと書かれていますので、自分の足でもペダルをこぐ電動アシスト自転車のようです。そくて電動アシスト自転車なら、言うまでもなく既に普及しています。
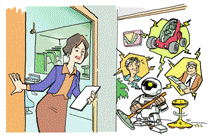 電動アシスト自転車は、電動オートバイにならないよう、むしろ法令で出力が抑えられているくらいで、既に充分な機能を持っています。電池の容量には多少改善の余地があるかも知れませんが、これ以上進化したら、電気オートバイにするしかありません。
電動アシスト自転車は、電動オートバイにならないよう、むしろ法令で出力が抑えられているくらいで、既に充分な機能を持っています。電池の容量には多少改善の余地があるかも知れませんが、これ以上進化したら、電気オートバイにするしかありません。つまり自転車専用レーンが作られていないだけで、この部分だけは2025年を待たずに実現可能なわけです。これがあるべき未来の姿ならば、必要なのはイノベーションではなく政治です。この例のみでは決めつけられませんが、技術や科学が進歩しても、政治や行政が変わらなければ実現しないことも多そうです。
自転車を未来の乗り物だと言うつもりはありませんが、有機的に機能する都市交通システム全体としてなら、充分イノベーションとなりうる存在です。それこそ、技術の粋を集めて作った次世代型の省エネ高機能タイプの高価格なクルマがそっぽを向かれ、人々は自転車を選択するかも知れません。
イノベーションを否定するものではありませんが、夢のような未来の予想図が、なんとなく空々しく感じられるのは、政治に期待できないことにも原因がありそうです。談合や天下り、利権や既得権にまみれた政官財の癒着や、政治や行政の仕組みにもイノベーションの必要がありそうです。
政府がまとめて、イノベ家(笑)の一日なんてやられると陳腐に見えてしまいますが、それぞれの技術はすごいものが多いですし、期待したいものもたくさんあります。ワクワクするような未来が本当に実現するような社会になって欲しいものですね。
関連記事
ベロシティという都市の理想
実現の可能性はともかく、夢のような自転車未来都市構想がある
ふだん使わないものを生かす
こんな突飛な空想が現実になることも、ないとは言えないだろう
夢から覚めた現実的未来都市
交通の未来を担うのは、こんな自転車輸送システムかも知れない

Amazonの自転車関連グッズ
Amazonで自転車関連のグッズを見たり注文することが出来ます。

Posted by cycleroad at 23:30│Comments(2)│TrackBack(0)
この記事へのトラックバックURL
この記事へのコメント
そこまで来たら私は嫌ですね、
ナンせロボットや電子管理された生活なんて・・
いくら現在の病気が無くなっても運動不足に新しい病が出来るでしょうね。
率直に今以上の進化は危険だと思います。
ぶつからない車とか危機管理が出来なくなりますし。
今まで機械と向き合っての"感"が無くなると思います
知ってる人でも母に高齢者用の乗り物?を買ってあげたらぼけたそうです、
やはり生き物としての自覚を失ったらまずいです。
ナンせロボットや電子管理された生活なんて・・
いくら現在の病気が無くなっても運動不足に新しい病が出来るでしょうね。
率直に今以上の進化は危険だと思います。
ぶつからない車とか危機管理が出来なくなりますし。
今まで機械と向き合っての"感"が無くなると思います
知ってる人でも母に高齢者用の乗り物?を買ってあげたらぼけたそうです、
やはり生き物としての自覚を失ったらまずいです。
Posted by 田舎者 at March 03, 2007 19:51
田舎者さん、こんにちは。コメントありがとうございます。
未来予測がイマイチ魅力的に見えないのは、そうした部分もあるのでしょうね。文明が発達して豊かになり、ラクになった分運動不足になって、お金を払ってジムで運動して体重を減らす生活というのも、そもそも矛盾と無駄に満ちているように思えます。ますます人間本来の姿からずれて行く部分もあるでしょう。
高度に自動化されたり、人間の五感で理解出来る範囲を超えて機械が発展するのは、おっしゃるように、かえって危険になることもありそうです。
使わなくなると退化したり弱くなる人間の器官も少なくないでしょうし、いったんラクになると元に戻れないのも問題ですね。今さら冷房のない生活が考えられないように、いったん手に入れた文化的で進んだ生活は、いかに地球環境に負荷をかけていても、なかなか後戻りできません。その辺も問題と言えそうですね。
未来予測がイマイチ魅力的に見えないのは、そうした部分もあるのでしょうね。文明が発達して豊かになり、ラクになった分運動不足になって、お金を払ってジムで運動して体重を減らす生活というのも、そもそも矛盾と無駄に満ちているように思えます。ますます人間本来の姿からずれて行く部分もあるでしょう。
高度に自動化されたり、人間の五感で理解出来る範囲を超えて機械が発展するのは、おっしゃるように、かえって危険になることもありそうです。
使わなくなると退化したり弱くなる人間の器官も少なくないでしょうし、いったんラクになると元に戻れないのも問題ですね。今さら冷房のない生活が考えられないように、いったん手に入れた文化的で進んだ生活は、いかに地球環境に負荷をかけていても、なかなか後戻りできません。その辺も問題と言えそうですね。
Posted by cycleroad at March 05, 2007 23:25
※全角800字を越える場合は2回以上に分けて下さい。(書込ボタンを押す前に念のためコピーを)