 あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。January 01, 2011
日本のお正月にあるべきもの
 あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。 今年も、さまざまな角度から自転車の話題を取り上げ、マイペースで更新していこうと思っています。よろしければお付き合いください。記事へのご意見・ご感想、こんな話もあるよといった情報などあれば、コメント欄に書き込んでいただければ幸いです。
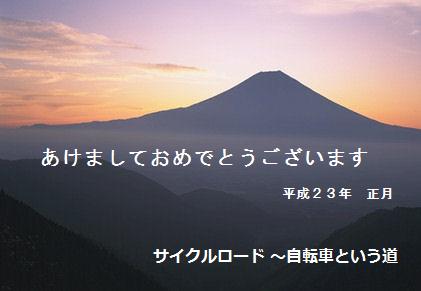
さて、2011年が明けました。今年も日本全国津々浦々、いつもと変わらぬ日本のお正月の光景が広がっていることでしょう。このブログも帰省した先で、おせち料理をつまみながら、あるいは、お酒を飲みながらご覧になっているという方も多いかも知れません。

 お正月は家族や親せきが集まり、大勢で食卓を囲んでいるお宅も多いことでしょう。当然、お膳にあがるのは、お節料理です。地域の伝統のおせち料理や、各家庭の味が詰まった「うちのおせち」が帰省の楽しみという方も多いのではないでしょうか。
お正月は家族や親せきが集まり、大勢で食卓を囲んでいるお宅も多いことでしょう。当然、お膳にあがるのは、お節料理です。地域の伝統のおせち料理や、各家庭の味が詰まった「うちのおせち」が帰省の楽しみという方も多いのではないでしょうか。
ただ最近は、おせちは作るものではなく買うものになりつつあるようです。デパートやスーパー、通販で買う人もいます。お正月ということもあって、なかなかいい値段のおせちも売れるようで、売る側も趣向をこらして高級おせちを売り込もうと力が入っています。
中には、有名フランス料理のシェフがつくる、フレンチのおせちとか、イタリアンのおせちなどまであります。私は食べたことがないのでわかりませんが、フレンチやイタリアンの料理を食べて、果たしてお正月という気分がするものなのでしょうか。
最近の子供たちには、洋食系のほうが口に合うのも一因なのでしょう。おせち料理の中に、フライドチキンやフライドポテト、ハンバーグなどが欲しいと思っている子供も多いかも知れません。近頃は大人にも、正月におせち料理をいただくことにこだわらない、実際に食べない人が増えているといいます。
 お節は、あらかじめ作っておくものではなく、買うのが普通と思っている子供もいます。普段の日も出来あいのお惣菜が多い家庭では、買ってくるお節も、「ふだんのおかず」のちょっと高級なものくらいにしか思っていなかったりするのでしょう。伝統のおせち料理は消えていく運命なのでしょうか。
お節は、あらかじめ作っておくものではなく、買うのが普通と思っている子供もいます。普段の日も出来あいのお惣菜が多い家庭では、買ってくるお節も、「ふだんのおかず」のちょっと高級なものくらいにしか思っていなかったりするのでしょう。伝統のおせち料理は消えていく運命なのでしょうか。
言うまでもなく、おせち料理は日本の食文化であり、遠く平安時代から受け継がれているものです。当時、宮中では季節の変わり目の日、「節」の日に、天皇臨席の「節会」という行事が催されていました。この時に出される料理が「節供(せっく)」、「御節供料理」であり、これがお節料理の起源と言われています。
よく、テレビの天気予報で、今日は二十四節気の一つの大寒ですとか、啓蟄ですなどと言うのを聞きます。これが季節の変わり目、「節」です。日本には四季があると言いますが、昔は四季どころか二十四もあったわけです。「季節」という言葉の語源も、この二十四節気から来ていると言われています。
ちなみに、「節」の下に七十二の「候」があり、一つの候は5日でした。かけると三百六十日、太陰暦の一年です。この二十四節気、七十二候から、「気候」という言葉も生まれています。昔は5日ごとに、気候が移り変わるのを感じていたのかも知れません。

 この季節の変わり目の節供(節句)のうち五つを、江戸時代に入って、幕府が公式な行事、祝日として定めました。今も桃の節句や端午の節句として残っています。このうち、最もお祝い色の濃い正月の料理だけが残り、今のおせち料理となったわけです。
この季節の変わり目の節供(節句)のうち五つを、江戸時代に入って、幕府が公式な行事、祝日として定めました。今も桃の節句や端午の節句として残っています。このうち、最もお祝い色の濃い正月の料理だけが残り、今のおせち料理となったわけです。
おせち料理を、お重に詰めるのは、めでたさを重ねるという縁起担ぎであり、お正月にいつ来客があっても、おもてなしが出来るようにという工夫です。おもてなしの料理であると同時に、今年一年の無事を祈っていただく、晴れの料理でもあります。
内容に日もちする料理が多いのは、火の神を怒らせないよう、正月に台所で火を使うことを避けるという風習から来ています。もちろん、いつも料理をしてくれるお母さんをねぎらい、休んでもらうためという狙いもこめられていたはずです。
子供の頃、「黒豆は、まめに働けるように。」とか、「数の子は数が多いので子孫繁栄で縁起がいい。」「昆布巻きは、よろこぶことが増えるように。」「海老は背中が丸くなるまで長生きできるように。」「出世魚のぶりで出世出来るように。」など、両親や祖父母に言われながら食べたという人も多いに違いありません。

 かまぼこは紅白で縁起が良く、鯛は文字通りおめでたい、栗きんとんは「金団」で金運が上昇する、福盛椎茸は裏側も豪華に出来るくらい福が来るように、なんていうのもありました。人参も梅の形、大根も菊花の形です。筍は末広の扇の形に切られていました。蓮根は遠くまで見通せるようにと言われたものです。
かまぼこは紅白で縁起が良く、鯛は文字通りおめでたい、栗きんとんは「金団」で金運が上昇する、福盛椎茸は裏側も豪華に出来るくらい福が来るように、なんていうのもありました。人参も梅の形、大根も菊花の形です。筍は末広の扇の形に切られていました。蓮根は遠くまで見通せるようにと言われたものです。
今にして思えば、単なるこじつけや駄洒落じゃないかと思いますが、ある面、その通りです。江戸時代になり、庶民にも節供の習慣が広がって宮中の料理とは全く異なるものになった時に、当時の庶民のユーモアや洒落、あるいは「粋」が反映されて生まれた独自の料理なのです。味や保存方法などの工夫と共に、長く伝承されてきた、まさに食文化です。
料理に洒落をきかせ、縁起をかつぐのは江戸の文化だったわけです。しかし、粋な中にも当時の庶民の切実な思いが込められています。江戸時代は飢饉もたびたび起こりましたし、火事も多発しました。病も天災も、今とは違って、得体の知れない鬼や疫病神の仕業と信じられ、恐れられていた時代です。
言葉遊びの中にも、庶民の祈るような思いがにじんでいるのは間違いありません。時代が変わり、そんな迷信をいつまでも保存する必要はないと言えばそれまでですが、日本人の中に先祖代々受け継がれてきた伝統や文化を、簡単に捨てていいものではないでしょう。

 今どき、鰤を食べたからと言って出世するとは子供でも信じないでしょうが、少なくとも、我々の先祖が考えたり、畏敬の念を持ってきたものを尊重する心があってもいいと思います。科学の進歩で、ややもすると忘れがちな自然の恵みに感謝する気持ちも忘れたくないものです。
今どき、鰤を食べたからと言って出世するとは子供でも信じないでしょうが、少なくとも、我々の先祖が考えたり、畏敬の念を持ってきたものを尊重する心があってもいいと思います。科学の進歩で、ややもすると忘れがちな自然の恵みに感謝する気持ちも忘れたくないものです。
縁起をかつぐべきとは言いませんが、いまだに大自然の脅威の前には、人間の力など小さなものに過ぎません。気候や自然現象を制御しようと考えるのは、人類の驕りかも知れません。母なる自然に対し、謙虚になる気持ちも必要でしょう。
お節料理は、寿司や天ぷらなどと同じように残していきたい日本の食文化だと思います。日本のお正月の風景の一つでもあり、大切にしたい風習です。お節を作ってくれた人に感謝し、先祖に感謝し、今年もお正月を迎えられることに感謝しながらいただきたいものです。


今年も、いろいろな話題を取り上げていきたいと考えています。直接、日々の自転車ライフには役立たない情報も多いとは思いますが、雑談のネタにでもしていただければと思っています。本年もよろしくお願いいたします。
関連記事

 大きくなる程減っていくもの
大きくなる程減っていくもの
最近消えていく一方の由緒ある地名も一つの文化的資産だと思う。
たたんで持ち歩く先人の知恵
古くから伝わる先人たちの知恵も、失われていく運命なのだろうか。
外国人の目にはどう映るのか
日本の伝統文化を大切にし、また活かすことが国益にもつながる。
愛着のわくお気に入りの一台
伝統ある自転車古い自転車を大切に乗り続けている人たちもいる。
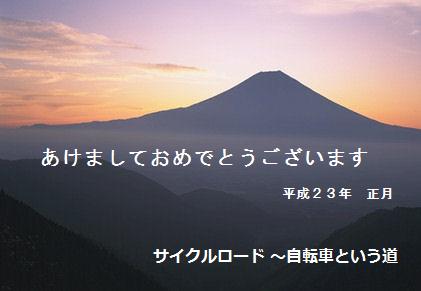
さて、2011年が明けました。今年も日本全国津々浦々、いつもと変わらぬ日本のお正月の光景が広がっていることでしょう。このブログも帰省した先で、おせち料理をつまみながら、あるいは、お酒を飲みながらご覧になっているという方も多いかも知れません。

ただ最近は、おせちは作るものではなく買うものになりつつあるようです。デパートやスーパー、通販で買う人もいます。お正月ということもあって、なかなかいい値段のおせちも売れるようで、売る側も趣向をこらして高級おせちを売り込もうと力が入っています。
中には、有名フランス料理のシェフがつくる、フレンチのおせちとか、イタリアンのおせちなどまであります。私は食べたことがないのでわかりませんが、フレンチやイタリアンの料理を食べて、果たしてお正月という気分がするものなのでしょうか。
最近の子供たちには、洋食系のほうが口に合うのも一因なのでしょう。おせち料理の中に、フライドチキンやフライドポテト、ハンバーグなどが欲しいと思っている子供も多いかも知れません。近頃は大人にも、正月におせち料理をいただくことにこだわらない、実際に食べない人が増えているといいます。
 お節は、あらかじめ作っておくものではなく、買うのが普通と思っている子供もいます。普段の日も出来あいのお惣菜が多い家庭では、買ってくるお節も、「ふだんのおかず」のちょっと高級なものくらいにしか思っていなかったりするのでしょう。伝統のおせち料理は消えていく運命なのでしょうか。
お節は、あらかじめ作っておくものではなく、買うのが普通と思っている子供もいます。普段の日も出来あいのお惣菜が多い家庭では、買ってくるお節も、「ふだんのおかず」のちょっと高級なものくらいにしか思っていなかったりするのでしょう。伝統のおせち料理は消えていく運命なのでしょうか。言うまでもなく、おせち料理は日本の食文化であり、遠く平安時代から受け継がれているものです。当時、宮中では季節の変わり目の日、「節」の日に、天皇臨席の「節会」という行事が催されていました。この時に出される料理が「節供(せっく)」、「御節供料理」であり、これがお節料理の起源と言われています。
よく、テレビの天気予報で、今日は二十四節気の一つの大寒ですとか、啓蟄ですなどと言うのを聞きます。これが季節の変わり目、「節」です。日本には四季があると言いますが、昔は四季どころか二十四もあったわけです。「季節」という言葉の語源も、この二十四節気から来ていると言われています。
ちなみに、「節」の下に七十二の「候」があり、一つの候は5日でした。かけると三百六十日、太陰暦の一年です。この二十四節気、七十二候から、「気候」という言葉も生まれています。昔は5日ごとに、気候が移り変わるのを感じていたのかも知れません。

おせち料理を、お重に詰めるのは、めでたさを重ねるという縁起担ぎであり、お正月にいつ来客があっても、おもてなしが出来るようにという工夫です。おもてなしの料理であると同時に、今年一年の無事を祈っていただく、晴れの料理でもあります。
内容に日もちする料理が多いのは、火の神を怒らせないよう、正月に台所で火を使うことを避けるという風習から来ています。もちろん、いつも料理をしてくれるお母さんをねぎらい、休んでもらうためという狙いもこめられていたはずです。
子供の頃、「黒豆は、まめに働けるように。」とか、「数の子は数が多いので子孫繁栄で縁起がいい。」「昆布巻きは、よろこぶことが増えるように。」「海老は背中が丸くなるまで長生きできるように。」「出世魚のぶりで出世出来るように。」など、両親や祖父母に言われながら食べたという人も多いに違いありません。

今にして思えば、単なるこじつけや駄洒落じゃないかと思いますが、ある面、その通りです。江戸時代になり、庶民にも節供の習慣が広がって宮中の料理とは全く異なるものになった時に、当時の庶民のユーモアや洒落、あるいは「粋」が反映されて生まれた独自の料理なのです。味や保存方法などの工夫と共に、長く伝承されてきた、まさに食文化です。
料理に洒落をきかせ、縁起をかつぐのは江戸の文化だったわけです。しかし、粋な中にも当時の庶民の切実な思いが込められています。江戸時代は飢饉もたびたび起こりましたし、火事も多発しました。病も天災も、今とは違って、得体の知れない鬼や疫病神の仕業と信じられ、恐れられていた時代です。
言葉遊びの中にも、庶民の祈るような思いがにじんでいるのは間違いありません。時代が変わり、そんな迷信をいつまでも保存する必要はないと言えばそれまでですが、日本人の中に先祖代々受け継がれてきた伝統や文化を、簡単に捨てていいものではないでしょう。

縁起をかつぐべきとは言いませんが、いまだに大自然の脅威の前には、人間の力など小さなものに過ぎません。気候や自然現象を制御しようと考えるのは、人類の驕りかも知れません。母なる自然に対し、謙虚になる気持ちも必要でしょう。
お節料理は、寿司や天ぷらなどと同じように残していきたい日本の食文化だと思います。日本のお正月の風景の一つでもあり、大切にしたい風習です。お節を作ってくれた人に感謝し、先祖に感謝し、今年もお正月を迎えられることに感謝しながらいただきたいものです。

今年も、いろいろな話題を取り上げていきたいと考えています。直接、日々の自転車ライフには役立たない情報も多いとは思いますが、雑談のネタにでもしていただければと思っています。本年もよろしくお願いいたします。
関連記事
最近消えていく一方の由緒ある地名も一つの文化的資産だと思う。
たたんで持ち歩く先人の知恵
古くから伝わる先人たちの知恵も、失われていく運命なのだろうか。
外国人の目にはどう映るのか
日本の伝統文化を大切にし、また活かすことが国益にもつながる。
愛着のわくお気に入りの一台
伝統ある自転車古い自転車を大切に乗り続けている人たちもいる。

Amazonの自転車関連グッズ
Amazonで自転車関連のグッズを見たり注文することが出来ます。

Posted by cycleroad at 00:30│Comments(4)│TrackBack(0)
この記事へのトラックバックURL
この記事へのコメント
明けましておめでとうございます。
本年も安全に BikeLife が楽しめるような一年にしたいものですね。
いつも色々な角度からの情報を楽しく読ませていただいておりますが、
本年も 宜しくお願いいたします。
本年も安全に BikeLife が楽しめるような一年にしたいものですね。
いつも色々な角度からの情報を楽しく読ませていただいておりますが、
本年も 宜しくお願いいたします。
Posted by fischer at January 03, 2011 10:22
本年も素敵な記事を読ませていただきます。
宜しくお願いします。
やはり、お正月はお節ですね!
見ているだけでも、楽しくなります。
(と言っても海外旅行ばかりで、正月日本に居るのはここ数年ですが・・・。)
宜しくお願いします。
やはり、お正月はお節ですね!
見ているだけでも、楽しくなります。
(と言っても海外旅行ばかりで、正月日本に居るのはここ数年ですが・・・。)
Posted by ヨッシー at January 04, 2011 21:53
fischerさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
そうですね、安全で楽しい、いい一年になるといいですね。
いつもご覧いただき、またコメントをいただきありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
そうですね、安全で楽しい、いい一年になるといいですね。
いつもご覧いただき、またコメントをいただきありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
Posted by cycleroad at January 04, 2011 23:06
ヨッシーさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
海外でのお正月もいいですが、やはり日本のお正月は落ち着きますね。
おせちが美味しいと、つい、お酒もすすんでしまいます。
いつもご覧いただき、またコメントをいただきありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
海外でのお正月もいいですが、やはり日本のお正月は落ち着きますね。
おせちが美味しいと、つい、お酒もすすんでしまいます。
いつもご覧いただき、またコメントをいただきありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
Posted by cycleroad at January 04, 2011 23:10
※全角800字を越える場合は2回以上に分けて下さい。(書込ボタンを押す前に念のためコピーを)