 桜が満開になるところも出てきました。
桜が満開になるところも出てきました。March 25, 2018
通信会社の英断を期待したい
 桜が満開になるところも出てきました。
桜が満開になるところも出てきました。 関東では、季節外れの雪が降る寒い春分の日でしたが、その後は一気に暖かくなって、東京では平年より10日も早く桜の満開が発表されています。さて、そんな折りですが、今回は例によって最近の自転車関連のニュースをピックアップしてみたいと思います。
やれば出来てしまうので、スマホを使いながら自転車に乗ることの危険性を過小評価している人は多いでしょう。日常的に見かけますし、警察などの取締りや啓発にも一向に減る気配がありません。このような、ながらスマホの危険を啓発するキャンペーンの意義は否定しません。
キャンペーンを行うKDDIは、スマホを提供する通信企業としての危機感もあるのでしょう。ただ、VRも自分で体験しないことには実感がわかないでしょうし、動画で見たとしても、果たしてどれだけの人が考え方を改めるかという点では、心許ない気がします。
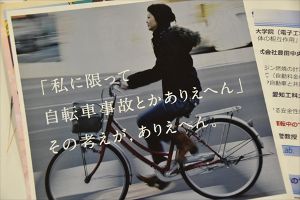 簡単なことではないと思いますが、いっそのことモーションセンサーやGPSを使って、動いている時にはスマホを使えなくしてしまうことは出来ないものでしょうか。他の企業との競争もあることですし、一企業に、そこまで期待するのは酷かも知れません。
簡単なことではないと思いますが、いっそのことモーションセンサーやGPSを使って、動いている時にはスマホを使えなくしてしまうことは出来ないものでしょうか。他の企業との競争もあることですし、一企業に、そこまで期待するのは酷かも知れません。
しかし、自社のスマホ全部に強制適用するのは困難だとしても、技術的に、そのような選択肢を設けることは可能だと思います。ながらスマホの危険を本当に理解すれば、うっかり使わないようにする意義は大きいですし、使えなくする仕様を選択する人もいるはずです。
そして、その結果がもたらす重大かつ深刻な結果を認識するにつれ、その選択をする人は増えていくのではないでしょうか。他の通信会社に先駆けて勇断すれば、反響も大きいでしょう。他社も追随すると思われます。世界的にも、そのリスクは問題になっているわけで、世界的に反響が広がるかも知れません。
素人考えではありますが、おそらく技術的には可能だろうと思います。VRでの体験によってアピールするのも悪いとは言いませんが、どれほどの効果が期待できるでしょうか。KDDIでなくてもいいですが、ぜひ通信会社のどこかの英断を期待したいものです。
電動アシスト自転車の普及拡大は続いていますが、利用者の4割弱の人が、電動アシストに独特な危険な経験をしたことがあるようです。その中の5割を「ペダルを踏んだ時の急発進」です。以前から指摘されてきた特性ですが、乗ってみて初めてわかることも多いのでしょう。
スマホを使いながら、もう一方の手には飲み物を持って女性を死亡させた女子大生の事故は、電動アシストの急発進が関わっていたという報道もあります。この事例は、そもそも危険な行為が多いので別としても、ながらスマホでなくても、急発進が死傷事故につながる可能性があるのは確かなようです。
最近は、ふだん利用していなくても、シェア自転車などで電動アシスト自転車に乗る機会が増えています。普通に乗るぶんには問題ないですし、ペダルが軽くて快適ですが、何かの拍子に急発進してしまうことがあることは、あらためて頭に入れておきたいところです。
冒頭の記事では、au損保1社だけでも、賠償額500万円以上の自転車事故は月に1件のペースで起きており、過去最高の賠償額はは8千万円に達していると言います。賠償事故の受付件数も2014年から倍増するなど急増していることも明らかにされています。
しかし、その次の記事のアンケートで、85%が知っているにも関わらず、保険に加入している人は56%にとどまっています。クルマやオートバイでも無保険で乗る人はいますが、わずかな割合です。ほとんどの人が、無保険で乗るのは無謀であり、イザという時のことを考えると割に合わないと感じているはずです。
よくよく考えてみると、それは自転車でも同じでしょう。スピードや衝撃度は相対的に小さいこともあり、高額の賠償責任を負う可能性は低いかも知れません。しかし、自転車でも事故を起こし、はずみで相手が死傷する可能性は十分あります。例え自転車であっても、賠償責任は変わりありません。
可能性は低いとしても、そのぶん保険料も安いわけですし、保険には加入しておくべきでしょう。自転車であろうとクルマやオートバイと同じことであり、万が一のことを考えれば、無保険は無謀であり、割に合わないという事実について、よく考えてみるべきではないでしょうか。
電動アシスト機構、バッテリーやモーターなどの技術の進化により、レースの世界へも影響が広がっています。フレームのパイプの中にモーターなどを隠す、いわゆる機材ドーピングが発覚し、とうとうX線検査が導入されるようです。身体へのドーピングに比べれば発見が容易なのが、せめてもの幸いと言えそうです。
以前に試乗した経験から、やはり重量があり、乗り心地的な面からも、個人的にはパンクレスタイヤを使う予定はありません。しかし、ママチャリに装着するのであれば、パンク修理、特にチューブ交換の困難さを考えると、リーズナブルと言えるかも知れません。メンテナンスしない人が多い点でも向いています。
これはローカルな記事なので、全国的な傾向なのかどうかはわかりません。ただ、パンクレスタイヤ装着車が人気となり、格安粗悪な自転車が敬遠されるようになるのであれば、自転車がパンクしただけで使い捨てのようにして、路上に放置するような人も減るでしょう。その点では、社会的にも望ましい傾向かも知れません。
ちょっと面白い記事が載っていました。丸の内では、身近に自転車通勤をする人がいる割合は4割にも上るようです。しかも、印象も悪くないようです。もちろんマナーなどには注意する必要がありますが、職場までの自転車通勤に対する一般的な認知度、好感度は上がっているのかも知れません。
中国での話ですが、過当競争が激化しているようです。補償金もとらず、利用料も2時間無料という価格破壊が起きています。事実上、ほとんど無料で利用できるでしょう。つまり、自転車の貸与そのもので収益を上げることは全く考えていないことになります。
大量の自転車を供給するにも、大きな初期投資が必要でしょう。にもかかわらず無料にするのは、シェア自転車の事実上の標準として、業界、あるいはその都市でのシェアを握れば、ビックデータを握ることになり、十分に採算が合うという計算なのに違いありません。中国の業者の狙いがよくわかります。
一方の日本では、東京でやっと9区で乗り入れです。もちろん、中国と環境が違い、ただ大量に自転車を供給するわけにはいかないでしょう。でも、自転車の貸与そのものではなく、ビックデータを握るという、中国の業者のような視点が、もう少しあってもいいような気がします。
 今回も、全国各地から自転車関連のニュースが届いています。相変わらず、自転車をテコに、観光客の誘致、地域振興を進めているところも多いようです。ニュースではありませんが、飛行機による輪行で、航空会社に預けた愛車の扱われ方を取材した記事がありました。
今回も、全国各地から自転車関連のニュースが届いています。相変わらず、自転車をテコに、観光客の誘致、地域振興を進めているところも多いようです。ニュースではありませんが、飛行機による輪行で、航空会社に預けた愛車の扱われ方を取材した記事がありました。
電車での輪行であれば、自分で持ち運ぶので、自分で注意出来ます。しかし、空港で荷物として預けてしまう場合は、どのように扱われるのか見えないため、不安があった人も多いのではないでしょうか。これを見る限り、航空会社に預けても乱雑に扱われる懸念はなさそうに見えます。
鉄道による輪行は行動範囲が広がりますし、ふだん行かないような場所へ行くことが出来ます。飛行機を使うことを考えれば、さらに範囲が広がるでしょう。週末の1泊2日でも、十分に遠出することが可能になります。陽気もよくなってきたことですし、輪行で遠出を考えてみてもいいかも知れません。
世界の保護主義化が、かつて世界大戦を招いたのに、平気でディールの手札にするとは世界の大迷惑ですね。
「自転車ながらスマホ」にNO、VRで体験
KDDI、ナビタイムジャパン、au損保が「自転車安全・安心プロジェクト」第2弾をスタートした。
2017年9月の第1弾に続くもので、この春4月1日から自転車利用に保険加入が義務化される京都府と連携し、「自転車ながらスマホ」の危なっかしさ状態を体感できるVRコンテンツなども用意して、自転車ながらスマホの撲滅、高額賠償への備えに関する意識を高める啓発活動を展開するという。
賠償額500万円以上の自転車事故、月イチで発生
京都府の犬井勇司氏(府民生活部、安心・安全まちづくり推進課長)は、この13年間は連続で交通事故が減っていることを明示し、それは自転車事故も同様であるとする。ただ、それらの交通事故のうち約2割を自転車事故が占め続けており、これはつまるところ、保険のない自転車事故がそれだけあるということを意味すると解説する。
自転車事故の相手は自動車、原付、歩行者の順で、ほぼ半分が出会い頭の事故だという。一般に事故の25%とされる出会い頭の事故が、自転車では半分というのは、自転車側に責任のある事故が増えてきていることを意味する。さらには、自転車と歩行者の事故の割合も増えてきている中で、その当事者の半分以上が30歳未満と若年層に集中しているそうだ。そこをきちんと啓発しなければならないと犬井氏はいう。
au損保の田中尚氏(営業企画室長)によれば、同社の場合、賠償額500万円以上の自転車事故は月に1件のペースで起きていて、過去最高の賠償額はは8,000万円に達しているそうだ。賠償事故の受付件数も2014年から倍増しているという。
「自転車ながらスマホ」の危険をVRで実感
発表会には、KDDIと共に「自転車ながらスマホ」の危険度を計測することを監修した愛知工科大学の小塚一宏氏(名誉・特任教授)が出席した。人間の視線で危険性を計測する研究活動を続けている研究者として、今回KDDIが制作したVRコンテンツ「自転車ながらスマホ」で、視野や反応速度の違いによって危険度が上がることを体感できる内容を監修した。
京都府庁で行われた実験に参加、今回のデモンストレーションにも登場した京都女子大学の富成朋美さん(UNN関西学生報道連盟)は「ながらスマホの危険性がよくわかった。ふたつの比較でながらスマホの危険を理解した。反応速度の違いを数値で比較できるのでよくわかる」とコメントする。
KDDIでは、au 公式Twitterアカウントの「自転車安全・安心プロジェクト」対象ツイートをリツイートすると1,000名にローソンのプレミアムロールケーキがもらえる「STOP! 自転車ながらスマホキャンペーン」を実施する。とにかく一人でも多くにその危険性を知って欲しいとKDDI株式会社の鳥光健太郎氏(CSR・環境推進室長)は訴える。(後略 2018/03/23 マイナビニュース)
やれば出来てしまうので、スマホを使いながら自転車に乗ることの危険性を過小評価している人は多いでしょう。日常的に見かけますし、警察などの取締りや啓発にも一向に減る気配がありません。このような、ながらスマホの危険を啓発するキャンペーンの意義は否定しません。
キャンペーンを行うKDDIは、スマホを提供する通信企業としての危機感もあるのでしょう。ただ、VRも自分で体験しないことには実感がわかないでしょうし、動画で見たとしても、果たしてどれだけの人が考え方を改めるかという点では、心許ない気がします。
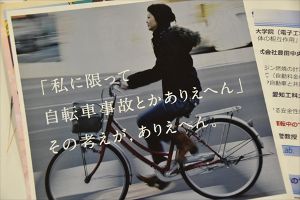 簡単なことではないと思いますが、いっそのことモーションセンサーやGPSを使って、動いている時にはスマホを使えなくしてしまうことは出来ないものでしょうか。他の企業との競争もあることですし、一企業に、そこまで期待するのは酷かも知れません。
簡単なことではないと思いますが、いっそのことモーションセンサーやGPSを使って、動いている時にはスマホを使えなくしてしまうことは出来ないものでしょうか。他の企業との競争もあることですし、一企業に、そこまで期待するのは酷かも知れません。しかし、自社のスマホ全部に強制適用するのは困難だとしても、技術的に、そのような選択肢を設けることは可能だと思います。ながらスマホの危険を本当に理解すれば、うっかり使わないようにする意義は大きいですし、使えなくする仕様を選択する人もいるはずです。
そして、その結果がもたらす重大かつ深刻な結果を認識するにつれ、その選択をする人は増えていくのではないでしょうか。他の通信会社に先駆けて勇断すれば、反響も大きいでしょう。他社も追随すると思われます。世界的にも、そのリスクは問題になっているわけで、世界的に反響が広がるかも知れません。
素人考えではありますが、おそらく技術的には可能だろうと思います。VRでの体験によってアピールするのも悪いとは言いませんが、どれほどの効果が期待できるでしょうか。KDDIでなくてもいいですが、ぜひ通信会社のどこかの英断を期待したいものです。
約4割が電動アシスト自転車で危なかった経験 自転車の意識調査
KDDIは、「自転車の安全・安心利用に関する意識調査」を実施し、その結果を発表した。調査対象は、日常的に自転車に乗る人、電動自転車に乗る人1,000名。
「自転車事故を起こした経験」を尋ねたところ、「ある」と回答したのは7.6%だった。「単独で事故を起した経験」は12.9%。対自動車は「出会い頭(右折時)」42.1%、自転車同士は「出会い頭(左折時)」40.0%、対歩行者は「出会い頭(左折時)」29.1%、単独は「進行中の追突」24.8%が多かった。
事故に遭った経験を見ると、「単独で事故に遭った」が11.9%だった。続いて、「自動車と事故に遭った経験」11.7%、「自転車同士で事故に遭った経験」8.9%。
「電動アシスト自転車の購入基準」は、64.8%を占めた「価格」が最も多かった。次いで「安全性」58.8%、「長距離移動や坂道の負担軽減」43.4%。
「実際に購入して良かったと思った点」は、「長距離移動や坂道の負担軽減」39.9%、「安全性」30.2%、「自転車に比較して足腰への負担軽減」24.2%。購入基準で高かった「価格」よりも「安全性」が高い結果となった。
「電動アシスト自転車で危ない経験をしたことがあるか」という設問に対しては、35.9%が「ある」と回答。「通勤利用」は47.1%、「通学利用」では59.1%が「ある」と回答している。
次に、電動アシスト自転車で危ない経験があると回答した人を対象に、「どのようなことで危ないと思ったか」を尋ねた。その結果、「ペダルを踏んだ時の急発進」49.9%が最も多かった。続いて、「重さによる転倒」40.4%、「乗降のよろめき」32.6%。
「電動アシスト自転車運転中のマナー違反」については、「マナー違反をしたことはない」37.1%がトップだった。続いて、「歩道を走る」30.7%、「雨の日の傘さし運転」23.3%。通勤利用では「雨の日の傘差し運転」36.4%、通学利用では「イヤホン」45.5%が最も多かった。
「スマートフォンを使用しながら自転車を運転し、女子大生が書類送検されたケースについて知っているか」を尋ねた設問では、73.9%が「知っている」と回答。自転車保険については「知っている」84.5%と認知度が高く、「加入している」が56.0%を占めた。加入理由は「加害者になるケースを想定して」55.6%が最も多かった。(2018年3月21日 レスポンス)
電動アシスト自転車の普及拡大は続いていますが、利用者の4割弱の人が、電動アシストに独特な危険な経験をしたことがあるようです。その中の5割を「ペダルを踏んだ時の急発進」です。以前から指摘されてきた特性ですが、乗ってみて初めてわかることも多いのでしょう。
スマホを使いながら、もう一方の手には飲み物を持って女性を死亡させた女子大生の事故は、電動アシストの急発進が関わっていたという報道もあります。この事例は、そもそも危険な行為が多いので別としても、ながらスマホでなくても、急発進が死傷事故につながる可能性があるのは確かなようです。
最近は、ふだん利用していなくても、シェア自転車などで電動アシスト自転車に乗る機会が増えています。普通に乗るぶんには問題ないですし、ペダルが軽くて快適ですが、何かの拍子に急発進してしまうことがあることは、あらためて頭に入れておきたいところです。
自転車保険の義務化広がる 自治体の制度と加入の確認を
自転車保険の加入を義務づける自治体が増加している。大人が運転している場合はもちろん、加害者が子供でも親が監督責任を問われる可能性があり、高額化する賠償金支払いに備えるのが目的だ。
一方、保険加入が義務づけられた原動機付自転車の5台に1台は契約が切れたままという。もうすぐ4月。通学通勤用の自転車、バイクを点検するとともに、保険の加入状況も確認したい。
◆相手のけがを補償
自転車は環境に穏やかで健康的、渋滞もなく、災害時の活用も期待できる。一方、電動アシスト自転車の普及や携帯電話の“ながら走行”で減速せずに歩行者にぶつかるなどして重大事故になるケースもあり、その場合の賠償金が高額化している。
こうした中で来月1日、埼玉、香川両県で自転車保険の加入を義務づける、または加入を呼びかける条例が施行される。すでに義務化したのは滋賀、大阪、鹿児島など6府県。推奨まで含めると、条例で呼びかける自治体は東京など14都府県に上る。
全国で初めて平成27年に条例化した兵庫県では、小学生の男児(11)が帰宅中、車道と歩道の区別がない道を歩行中の女性と衝突。女性は意識不明となり、神戸地裁は男児の親に約9500万円の支払いを命じた。(後略 2018.3.19 産経新聞)
冒頭の記事では、au損保1社だけでも、賠償額500万円以上の自転車事故は月に1件のペースで起きており、過去最高の賠償額はは8千万円に達していると言います。賠償事故の受付件数も2014年から倍増するなど急増していることも明らかにされています。
しかし、その次の記事のアンケートで、85%が知っているにも関わらず、保険に加入している人は56%にとどまっています。クルマやオートバイでも無保険で乗る人はいますが、わずかな割合です。ほとんどの人が、無保険で乗るのは無謀であり、イザという時のことを考えると割に合わないと感じているはずです。
よくよく考えてみると、それは自転車でも同じでしょう。スピードや衝撃度は相対的に小さいこともあり、高額の賠償責任を負う可能性は低いかも知れません。しかし、自転車でも事故を起こし、はずみで相手が死傷する可能性は十分あります。例え自転車であっても、賠償責任は変わりありません。
可能性は低いとしても、そのぶん保険料も安いわけですし、保険には加入しておくべきでしょう。自転車であろうとクルマやオートバイと同じことであり、万が一のことを考えれば、無保険は無謀であり、割に合わないという事実について、よく考えてみるべきではないでしょうか。
自転車=トップレースにX線検査導入へ、機材の不正防止で
国際自転車競技連合(UCI)は機材に隠しモーターをつけるなどの不正行為を防止するため、グランツール(三大ステージレース)とトップレベルのクラシックレースでX線検査機器を搭載した車両を導入する。
関係者が20日、ロイターに明らかにした。ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリア、ブエルタの三大ステージレースの各ステージ終了後と、五大ワンデーレースのレース後にX線カメラで機材をチェックするという。
UCIでは昨年9月に就任したダビッド・ラパルティアン会長の下、技術的な不正の防止を重要課題の一つに掲げていた。
UCIは前会長の体制ではタブレット端末を用いて機材をスキャンしていたが、選手やチームスタッフからは不十分だと批判を受けていた。ツール・ド・フランスでは、隠しモーターを検知するために過去2大会で赤外線カメラが用いられていた。
自転車競技では2016年、ベルギーのファムケ・ファンデンドリエッシュがシクロクロス世界選手権で隠しモーターを付けた自転車を使用していたことが発覚し、UCIから6年の出場停止処分を受けた。(2018年3月22日 ロイター)
電動アシスト機構、バッテリーやモーターなどの技術の進化により、レースの世界へも影響が広がっています。フレームのパイプの中にモーターなどを隠す、いわゆる機材ドーピングが発覚し、とうとうX線検査が導入されるようです。身体へのドーピングに比べれば発見が容易なのが、せめてもの幸いと言えそうです。
パンクしないタイヤの自転車人気 入学シーズン、売り場に活気
中学や高校などの入学シーズンを前に、福井県内のホームセンターなどで自転車売り場がにぎわっている。ずらりと並んだピカピカの自転車に、子どもたちは気持ちを高ぶらせお気に入りの一台を品定めしている。
福井市新保北1丁目のヤスサキワイホーム新保店では、2月中旬から自転車売り場を拡大。桜の造花や「祝ご入学」と書かれたポップが店内を彩る。
2月の記録的な大雪により出足は鈍かったものの、3月に入り通学用自転車を買い求める新中学生らが訪れている。人気が高いのはパンクしない特殊なタイヤの自転車で、担当者によると「『よりいいものを』との保護者の思いから3万円以上の高価格帯が売れる」という。
3月下旬から増えてくるのは大学生や社会人で、1万円前後の手ごろな「ママチャリ」が人気。4月ごろまで商戦のピークは続くという。
通学用自転車を祖母に買ってもらった岩井瑠子さん(12)は「大きいけれど軽いのがお気に入り。中学校に行くのが楽しみ」と話していた。(2018年3月23日 福井新聞)
以前に試乗した経験から、やはり重量があり、乗り心地的な面からも、個人的にはパンクレスタイヤを使う予定はありません。しかし、ママチャリに装着するのであれば、パンク修理、特にチューブ交換の困難さを考えると、リーズナブルと言えるかも知れません。メンテナンスしない人が多い点でも向いています。
これはローカルな記事なので、全国的な傾向なのかどうかはわかりません。ただ、パンクレスタイヤ装着車が人気となり、格安粗悪な自転車が敬遠されるようになるのであれば、自転車がパンクしただけで使い捨てのようにして、路上に放置するような人も減るでしょう。その点では、社会的にも望ましい傾向かも知れません。
丸の内OL100人に大調査! 「自転車通勤男子」のNGな点とは?
コッチはこのほど、同社が運営するサイトCocci Pedaleにおいて、アンケート「自転車通勤男子のココがNG」の結果を発表した。同調査は3月14日、東京都丸の内周辺でOL100人を対象に街頭で行った。
自転車で通勤する男性は周囲にいるか尋ねたところ、「いる」は39%、「いない」は61%だった。
電車で通勤する男性と自転車で通勤する男性のどちらが印象がいいか尋ねると、最も多い回答は「自転車通勤」(57%)だった。次いで「どちらとも言えない」(36%)で、「電車通勤」は7%にとどまっている。
自転車で通勤する男性のNGなところはどんな点か聞くと、「交通マナー」(41%)という回答が最も多かった。具体的には、「スマホを持ったり見たりしながらの片手運転」「スピード出しすぎ」「ギリギリのすり抜け」などに注意してほしいとの声があがっている。
また、自動車通勤をしているという一部の回答者からは、「自動車との間隔が狭すぎる」「交通法規を守って欲しい」という意見もあった。「エチケット」(7%)と回答した人からは、「ペダルをこいだあとの体臭」「全身の汗」という声も寄せられている。会社だけでなく通勤途中の駐輪が気になると「駐輪場所」(6%)と回答した人もいた。
自転車で通勤する男性の好きなところを尋ねたところ、最も多い回答は「健康的」(51%)だった。「爽やか」(14%)、「エコ」(6%)といった意見も寄せられている。(2018/03/22 マイナビニュース)
ちょっと面白い記事が載っていました。丸の内では、身近に自転車通勤をする人がいる割合は4割にも上るようです。しかも、印象も悪くないようです。もちろんマナーなどには注意する必要がありますが、職場までの自転車通勤に対する一般的な認知度、好感度は上がっているのかも知れません。
深センでサービス開始のシェア自転車企業、当局の「違反行為、処罰する」を無視して路上に大量配置―中国
広東省メディアの金羊網は20日、シェア自転車大手の青橘単車が同省深セン市で、当局の「違反行為、処罰する」との警告を無視して、市内各所の路上に大量の自転車を置き続けていると報じた。
青橘単車は配車サービス大手の滴滴出行の傘下企業。中国では一般的に、シェア自転車企業としてアリババ系のofoやテンセント系のMobikeに次ぐ存在と見なされている。
金羊網によると、滴滴出行の関係者が、青橘単車は3月初頭に深セン市福田区で試験的サービスを開始していたと説明。5月までには同市にシェア自転車65万台を投入する計画という。
青橘単車は3月17日未明に、深セン市での正式サービスを開始したとした。一方で、市交通委員会は同日夜、交通や路上での営業活動など市街地における違反行為を取り締まる城市管理行政執法局と交通警察との合意によるとして、青橘単車の行為はルール違反として、放置した自転車をただちに回収するするよう求めた。
しかし金羊網によると、市内各所の路上に置かれた青橘単車の自転車は19日になっても増え続けている。青橘単車はさらに、「利用無料」のサービスを展開している。SNSを利用して月単位の登録をすれば、1日2回、2時間まで無料で利用できるという。同社の場合、従来からユーザー登録時の保証金も不要だ。
市交通委員会は19日夜になり改めて、「深セン市インターネット賃貸自転車規範管理整理行動実施方案」に基づくとして、取り締まりを強化すると表明。今後は「深セン経済特区外観と環境衛生管理条例」などの法に基づき、企業の違反行為に対する処罰を行うとした。
中国では2016年後半から、シェア自転車ビジネスが急拡大した。シェア自転車はスマートフォンにダウンロードしたアプリで極めて簡単に利用でき、地下鉄やバスなどを利用してから訪問先あるいは自宅に到着するまでの都市部交通における「最後の1キロメートル」を解決できるとして多くの人に歓迎された。
中国インターネット情報センター(CNNIC)によると、17年6月には1億600万人だったシェア自転車ユーザー(各運営企業への登録者)は、同年12月には2億2100万人に達した。
一方で、街路に無秩序に放置される自転車が大量に発生するなどの問題も出た。さらに、参入企業が殺到して過当競争が発生し倒産する企業が続出。多くの場合、ユーザー登録時に保証金を支払うシステムだったので、保証金やチャージされた前払金が戻ってこない事態も続出した。
中国人は一般的に、ビジネスについて「勝敗を分けるのはタイミング」との感覚が強い。そのため、新手のビジネスが登場して「前途有望」と見なされると、大量の企業が「それっ」とばかりに参入する現象がしばしば発生する。このような特性は、社会や経済を前進させる原動力になっていると同時に、行政側の対応が後手に回ることによる弊害や、過当競争による倒産や撤退が多発することにつながっている。(2018年3月23日 レコードチャイナ)
中国での話ですが、過当競争が激化しているようです。補償金もとらず、利用料も2時間無料という価格破壊が起きています。事実上、ほとんど無料で利用できるでしょう。つまり、自転車の貸与そのもので収益を上げることは全く考えていないことになります。
大量の自転車を供給するにも、大きな初期投資が必要でしょう。にもかかわらず無料にするのは、シェア自転車の事実上の標準として、業界、あるいはその都市でのシェアを握れば、ビックデータを握ることになり、十分に採算が合うという計算なのに違いありません。中国の業者の狙いがよくわかります。
自転車シェアリング 9区で相互乗り入れ可能に 来月から品川、大田が参加 /東京
広域で利用ができる「自転車シェアリング」について、品川、大田両区が4月1日から新たに参加する。現在は都心部7区が実施しているが、2区の参加で計9区で利用できることになった。
自転車シェアリングとは、自転車を置く拠点(ポート)で、利用者に有料で貸し出す仕組み。会員になれば誰でも利用できる。現在実施しているのは、千代田▽中央▽港▽新宿▽文京▽江東▽渋谷−−の7区。都環境局によると、7区で計359カ所のポートがあり、電動アシスト自転車4850台を用意している。料金は30分150円で、24時間いつでも借りたり返したりすることができる。
江東区が2012年、2020年東京五輪・パラリンピックに向け、移動手段の一つとして自転車のシェアリングを始めたのを皮切りに、都心の区が次々と導入。使用率が高く好評のため、これまで区内のみに限定していた2区も、他区との相互乗り入れを始めることになった。
品川区は今年度内にポート45カ所、自転車500台を用意。大田区は1月末現在、ポートや有人窓口39カ所、自転車150台となっている。都もシェアリングに補助金を拠出しており、都の担当者は「自転車は小回りがきいて、利用者にもメリットがある。今後もシェアサイクルを広げていきたい」と話している。(毎日新聞 2018年3月18日)
一方の日本では、東京でやっと9区で乗り入れです。もちろん、中国と環境が違い、ただ大量に自転車を供給するわけにはいかないでしょう。でも、自転車の貸与そのものではなく、ビックデータを握るという、中国の業者のような視点が、もう少しあってもいいような気がします。
自転車で巡ろう 和歌山県内の名所(和歌山)
“尾道に似合うちょっといい自転車” 新ブランドを発売(広島)
湖国の人たち 自転車修理店内にビワイチサロン開設(滋賀)
歩道に自転車通行路(神奈川)
平城宮跡歴史公園 新たな観光拠点(奈良)
かごりん 新自転車お目見え 明治維新150年号(鹿児島)
自転車の楽しみPR ワカカツマップ刷新(和歌山)
ランニング・自転車でポイント巡る 徳島・海陽でレース(徳島県)
ワースト逆戻り 悩む足立区 昨年の犯罪件数6年ぶり増(東京)
自転車駆って100人社寺巡り 出雲・松江(島根)
自転車で大刀洗巡ろう 町が無料レンタル 役場発着 (福岡)
ハイテクなシェア自転車 発進(和歌山)
五輪・パラ自転車のボランティア募集(静岡)
ANA飛行機輪行の裏側に潜入、「自転車は、お客様と一心同体」羽田〜松山間の輸送とは
遠いけれど輪行でサイクリングしてみたい場所がある。そんな時に速くて便利なのが飛行機輪行だ。しかし輪行初心者でもベテランサイクリストでも、電車やクルマとは違って目の届かない所に運ばれることに不安を覚える人もいるだろう。そこでCyclist編集部は空港内に潜入し、羽田〜松山空港間で運航する全日空(ANA)の便を追跡。預けた自転車が丁寧に運ばれるプロセスを取材した。(後略 2018/03/19 サンスポ)
 今回も、全国各地から自転車関連のニュースが届いています。相変わらず、自転車をテコに、観光客の誘致、地域振興を進めているところも多いようです。ニュースではありませんが、飛行機による輪行で、航空会社に預けた愛車の扱われ方を取材した記事がありました。
今回も、全国各地から自転車関連のニュースが届いています。相変わらず、自転車をテコに、観光客の誘致、地域振興を進めているところも多いようです。ニュースではありませんが、飛行機による輪行で、航空会社に預けた愛車の扱われ方を取材した記事がありました。電車での輪行であれば、自分で持ち運ぶので、自分で注意出来ます。しかし、空港で荷物として預けてしまう場合は、どのように扱われるのか見えないため、不安があった人も多いのではないでしょうか。これを見る限り、航空会社に預けても乱雑に扱われる懸念はなさそうに見えます。
鉄道による輪行は行動範囲が広がりますし、ふだん行かないような場所へ行くことが出来ます。飛行機を使うことを考えれば、さらに範囲が広がるでしょう。週末の1泊2日でも、十分に遠出することが可能になります。陽気もよくなってきたことですし、輪行で遠出を考えてみてもいいかも知れません。
世界の保護主義化が、かつて世界大戦を招いたのに、平気でディールの手札にするとは世界の大迷惑ですね。

Amazonの自転車関連グッズ
Amazonで自転車関連のグッズを見たり注文することが出来ます。

Posted by cycleroad at 13:00│Comments(2)
この記事へのコメント
移動中でも使えるから今のようにスマホが普及したのでは無いでしょうか
一番人を殺してるのは車です、じゃあ車を動けなくすれば事故は起こりません
でも動けないのはもう車では無いです
助手席でスマホを使っている人、電車に乗っている人
ナビとして使っている人
移動しながら使えるから価値のあるものでは無いでしょうか
センサーで人に近ずいたら警告するとか(人混みでは使えないですね)
安全に使える方法へ進むのが良いのではと私は思います
一番人を殺してるのは車です、じゃあ車を動けなくすれば事故は起こりません
でも動けないのはもう車では無いです
助手席でスマホを使っている人、電車に乗っている人
ナビとして使っている人
移動しながら使えるから価値のあるものでは無いでしょうか
センサーで人に近ずいたら警告するとか(人混みでは使えないですね)
安全に使える方法へ進むのが良いのではと私は思います
Posted by あるふぁ at March 29, 2018 23:26
あるふぁさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
屋外でも使えるからスマホが便利なのは言うまでもありません。ただ、移動中に使えるのと、移動しながら使うのとは分けて考える必要があると思います。
包丁を殺人に使う人間が悪いのであって、包丁は悪くないというのと同じで、スマホそのものが悪いとは言いません。一部の人の使い方が悪いということでしょう。
動かなくしたらクルマでなくなりますが、スマホは止まって使っても便利です。たしかに、助手席や電車移動中に使えないと不便ですが、例えば電車移動を検知したら使えるようにすることは技術的に可能でしょう。全て使えなくすると不便ですが、危険なケースでは、うっかり使ってしまわないような工夫があってもいいでしょう。
実際に、ながらスマホで死傷事故が起きています。被害者はもちろん、加害者も不幸な状況に陥ります。
何の製品でもそうですが、使い方を誤ると危険な場合、それを防ぐための機能や設計が求められます。スマホにも、そのような機能があってもいいのではないでしょうか。
屋外でも使えるからスマホが便利なのは言うまでもありません。ただ、移動中に使えるのと、移動しながら使うのとは分けて考える必要があると思います。
包丁を殺人に使う人間が悪いのであって、包丁は悪くないというのと同じで、スマホそのものが悪いとは言いません。一部の人の使い方が悪いということでしょう。
動かなくしたらクルマでなくなりますが、スマホは止まって使っても便利です。たしかに、助手席や電車移動中に使えないと不便ですが、例えば電車移動を検知したら使えるようにすることは技術的に可能でしょう。全て使えなくすると不便ですが、危険なケースでは、うっかり使ってしまわないような工夫があってもいいでしょう。
実際に、ながらスマホで死傷事故が起きています。被害者はもちろん、加害者も不幸な状況に陥ります。
何の製品でもそうですが、使い方を誤ると危険な場合、それを防ぐための機能や設計が求められます。スマホにも、そのような機能があってもいいのではないでしょうか。
Posted by cycleroad at March 30, 2018 22:09
※全角800字を越える場合は2回以上に分けて下さい。(書込ボタンを押す前に念のためコピーを)