 最近、ジェンダーという言葉をよく耳にします。
最近、ジェンダーという言葉をよく耳にします。December 10, 2021
女性は自転車に乗らないもの
 最近、ジェンダーという言葉をよく耳にします。
最近、ジェンダーという言葉をよく耳にします。 ジェンダーフリーとか、ジェンダー平等といった言い方で、性別による社会的差別をなくしていこうという文脈で語られます。世界的にも、あらためて性差による不平等が意識されることが多くなっています。持続可能な開発目標、SDGsにもジェンダーの平等が掲げられています。
男女格差は存在しています。世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数によれば、日本は世界の153ヵ国中121位とかなり低い位置にいます。経営者や国会議員における女性の比率の低さは明らかですし、非正規雇用の割合は高くなっています。賃金や待遇などにも格差はあるでしょう。
格差や不平等だけでなく、社会的な慣習や文化的な伝統などによる性差もあります。例えば、男性が働き、女性は家庭を守るものとか、男性は男性らしく、女性は女性らしくとか、男性はスカートをはくものではない、女子が黒いランドセルを背負うのはおかしい、といった固定観念も多々存在しています。
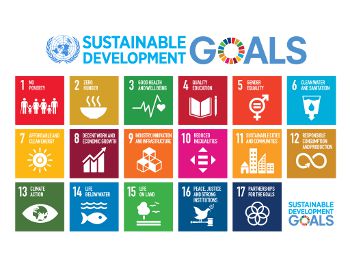

生まれた時からジェンダーへの慣習的な考え方が存在していたため、無意識にそのような考え方になっている人も多いでしょう。周囲の女子が皆スカートをはいていれば、疑うことなくはく子どもは多いはずです。自分の判断ではくのは構いませんが、そういうものと押し付けるのは間違いでしょう。
女性であってもスカートをはきたくない人はいます。LGBTQの議論とも重なる部分がありますが、そうでなくても、女性はスカートをはくものという固定観念は、ジェンダーフリーに逆行する考え方です。このような、無意識にある固定観念というのは多いに違いありません。
生物学的に、女性しか出産できないのは確かですが、女性だけが子育てをするというのは違うでしょう。体力・筋力的に男女差があるのは当然としても、学校の制服が男女別に決まっていて、それを強いられる必要があるでしょうか。#MeToo 運動というのもありましたが、セクハラなどの背景にもジェンダーの問題があるはずです。


ところで、自転車についても、ジェンダーによる思い込みがあるのではないでしょうか。宗教や政治的な背景もありますが、イスラム教の国などで女性が自転車に乗れないのもそうです。少し前に取り上げた、アイルランドの女子生徒が中学生になると自転車に乗らなくなるのも、固定観念が影響しているはずです。
自転車レースの世界は男性優位です。例えば、ロードレースの最高峰、ツール・ド・フランスは男性だけです。女性版のレース開催を望む声もあって、かつて、“Tour de France Feminin”として開催されていたこともあるのですが、観客が少なく、スポンサーの獲得が難しかったため廃止されました。
近年、また実現させようという声もあるようです。署名活動なども行われたりしています。自転車レースの世界にも男女平等を実現するべきだとの声もあるのです。しかし、逆に言えば、自転車が男性のスポーツのようになっている現実があると言えるでしょう。


レースでなく趣味としても、スポーツバイクに乗る女性は男性より圧倒的に少ない割合です。乗りたいと思わない、自分の意志で乗らないのはいいですが、もしかしたら、そこに固定観念が影響していないでしょうか。日本で、女性はママチャリに乗るのが普通という考え方も、ジェンダーフリーとは言えません。
ママチャリという呼び方も問題か知れませんが、日本では、ママチャリで買い物に行ったり、子どもの送迎をする女性が大勢います。しかし、年代によっては女性はあまり乗りませんし、自転車の趣味は男性のものと思われている傾向もあります。女性がスポーツバイクを買おうとすると、サイズの選択が乏しかったりします。


多くの国では、女性が自転車に乗ってはいけないことはありませんが、無意識の固定観念が影響して乗らないということもあるでしょう。女性たち自身が無意識のうちに自転車を敬遠しているのではないか、もっと女性が自転車に乗ってもいいはず、と考えた人たちがいます。
トルコはイズミル在住の女性、Sema Gur さんや、Pinar Pinzuti さんたちのグループです。トルコはイスラム教信者が圧倒的に多い国ですが、政教分離が徹底されており、イスラムの世界では屈指の世俗主義国家です。ですから、女性が自転車に乗れないわけではありません。ただ、男性と比べて少ないのは確かです。




彼女たちが始めたのが、“Fancy Women Bike Ride (Suslu Kadinlar Bisiklet Turu)”です。毎年9月の世界カーフリーデーに開催されるイベントです。女性たちが自転車を持って広場に集まり、楽しく着飾って一緒に自転車に乗ります。女性の誰もが自転車に乗れることをアピールします。
みんなで楽しく自転車に乗るイベントですが、自転車が女性にも開放されていることを示し、より多くの女性が都市においてサイクリングをすることを奨励する、女性による女性のためのイベントです。多くの女性が自転車に乗っていることを女性に気づいてもらいたいという意図もあります。




レースではなく、ライドイベントです。スピードは出さず、皆で楽しく乗って、沿道の観客に笑顔で手を振ります。カラフルなドレスを着て、ハイヒールで、花で飾られた自転車に乗ります。そして、参加する女性には、ふだん自転車に乗らない友人、母親、叔母、姉妹を誘って連れてくることを奨励しています。
みんなで楽しく乗ることで、あるいは試してもらうことで、自転車の楽しさを知り、女性たちがもっと気軽に乗るようになってほしいとの願いがあるのです。特にドレスコードで制限されているわけではありませんが、みなオシャレをして自転車に乗ります。




サイクリングに不慣れな人は皆でサポートします。主催者たちは、自転車の楽しさ、喜び、娯楽としての自転車を知ってほしいと考えています。決してレースだけではなく、汗をかいて疲れるだけの移動手段ではないことを知らせたいのです。2013年に始めましたが、口コミやSNSで広がり、300人も集まりました。
翌年は参加者が2倍になり、テレビや活字メディアも取材に来ました。2015年には、イズミルだけでなく、イスタンブールやアンカラ、アダナ、エスキセヒル、マルマリス、ボドルムなどの都市にも広がりました。2016年には、数千人の女性たちが28の都市の広場を埋め尽くしました。




2017年には50都市、2018年にはトルコ以外にもイタリア、ドイツ、スイスなどの70都市に広がります。EUの運輸委員会によって国際的な女性イベントとして正式に認められました。2019年、世界の115都市に広がり、この年に世界で最も成功した草の根運動とされました。
2020年には25か国、150の都市、2021年には30か国、少なくとも150以上の都市に広がり、2022年には世界中の数百の都市で同時開催されるはずです。カーフリーデーということで環境面の共感もありますが、女性のライドイベントとしては世界有数のものとなっています。




これだけ急速に広がったのは、女性たちの連帯ということもありますが、自転車に乗る楽しさを実感した人も多かったはずです。誰でも参加できて、運営はボランティア、いかなる機関やブランドとも関係しないことも要因だと考えられます。
彼女たちは、自転車で通勤することを頼むわけではありません。クルマでなく自転車で休日に出かけるよう呼びかけるわけでもありません。ただ、この日に皆で楽しく乗るだけです。でも、それが多くの女性たちに、自転車に乗るという選択肢に気づかせ、乗ってみようかなと思わせたに違いありません。




自転車に乗る選択肢を気づかせたということは、一般的に女性は乗らないものという固定観念があったと気づかせたことでもあるでしょう。スポーツとしての自転車を、あまり魅力的と思わない人たちでも、気軽な移動手段として、気晴らしとして、楽しむために乗ってもいいことに気づいたのかも知れません。
ジェンダーフリーを声高に叫んでいるわけではありません。楽しくオシャレをして乗るだけです。でも、女性のイベントとして開催することで、多くの女性に何かの気づき、解放をもたらしたようです。少なくとも自転車の面でのジェンダーフリーに一石を投じたと言えそうです。
◇ 日々の雑感 ◇
理化学研究所が日本人のコロナ患者の重症や死亡が、欧米に比べて非常に少ない謎の要因、「ファクターX」の一部を解明したと報じられています。本当なら日本人にとって幸運ですし、オミクロンも広がらないことを祈ります。
男女格差は存在しています。世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数によれば、日本は世界の153ヵ国中121位とかなり低い位置にいます。経営者や国会議員における女性の比率の低さは明らかですし、非正規雇用の割合は高くなっています。賃金や待遇などにも格差はあるでしょう。
格差や不平等だけでなく、社会的な慣習や文化的な伝統などによる性差もあります。例えば、男性が働き、女性は家庭を守るものとか、男性は男性らしく、女性は女性らしくとか、男性はスカートをはくものではない、女子が黒いランドセルを背負うのはおかしい、といった固定観念も多々存在しています。
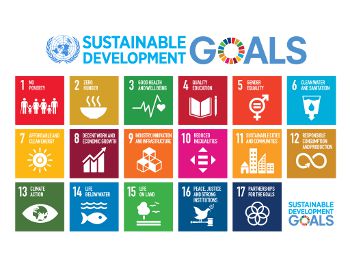

生まれた時からジェンダーへの慣習的な考え方が存在していたため、無意識にそのような考え方になっている人も多いでしょう。周囲の女子が皆スカートをはいていれば、疑うことなくはく子どもは多いはずです。自分の判断ではくのは構いませんが、そういうものと押し付けるのは間違いでしょう。
女性であってもスカートをはきたくない人はいます。LGBTQの議論とも重なる部分がありますが、そうでなくても、女性はスカートをはくものという固定観念は、ジェンダーフリーに逆行する考え方です。このような、無意識にある固定観念というのは多いに違いありません。
生物学的に、女性しか出産できないのは確かですが、女性だけが子育てをするというのは違うでしょう。体力・筋力的に男女差があるのは当然としても、学校の制服が男女別に決まっていて、それを強いられる必要があるでしょうか。#MeToo 運動というのもありましたが、セクハラなどの背景にもジェンダーの問題があるはずです。


ところで、自転車についても、ジェンダーによる思い込みがあるのではないでしょうか。宗教や政治的な背景もありますが、イスラム教の国などで女性が自転車に乗れないのもそうです。少し前に取り上げた、アイルランドの女子生徒が中学生になると自転車に乗らなくなるのも、固定観念が影響しているはずです。
自転車レースの世界は男性優位です。例えば、ロードレースの最高峰、ツール・ド・フランスは男性だけです。女性版のレース開催を望む声もあって、かつて、“Tour de France Feminin”として開催されていたこともあるのですが、観客が少なく、スポンサーの獲得が難しかったため廃止されました。
近年、また実現させようという声もあるようです。署名活動なども行われたりしています。自転車レースの世界にも男女平等を実現するべきだとの声もあるのです。しかし、逆に言えば、自転車が男性のスポーツのようになっている現実があると言えるでしょう。


レースでなく趣味としても、スポーツバイクに乗る女性は男性より圧倒的に少ない割合です。乗りたいと思わない、自分の意志で乗らないのはいいですが、もしかしたら、そこに固定観念が影響していないでしょうか。日本で、女性はママチャリに乗るのが普通という考え方も、ジェンダーフリーとは言えません。
ママチャリという呼び方も問題か知れませんが、日本では、ママチャリで買い物に行ったり、子どもの送迎をする女性が大勢います。しかし、年代によっては女性はあまり乗りませんし、自転車の趣味は男性のものと思われている傾向もあります。女性がスポーツバイクを買おうとすると、サイズの選択が乏しかったりします。


多くの国では、女性が自転車に乗ってはいけないことはありませんが、無意識の固定観念が影響して乗らないということもあるでしょう。女性たち自身が無意識のうちに自転車を敬遠しているのではないか、もっと女性が自転車に乗ってもいいはず、と考えた人たちがいます。
トルコはイズミル在住の女性、Sema Gur さんや、Pinar Pinzuti さんたちのグループです。トルコはイスラム教信者が圧倒的に多い国ですが、政教分離が徹底されており、イスラムの世界では屈指の世俗主義国家です。ですから、女性が自転車に乗れないわけではありません。ただ、男性と比べて少ないのは確かです。




彼女たちが始めたのが、“Fancy Women Bike Ride (Suslu Kadinlar Bisiklet Turu)”です。毎年9月の世界カーフリーデーに開催されるイベントです。女性たちが自転車を持って広場に集まり、楽しく着飾って一緒に自転車に乗ります。女性の誰もが自転車に乗れることをアピールします。
みんなで楽しく自転車に乗るイベントですが、自転車が女性にも開放されていることを示し、より多くの女性が都市においてサイクリングをすることを奨励する、女性による女性のためのイベントです。多くの女性が自転車に乗っていることを女性に気づいてもらいたいという意図もあります。




レースではなく、ライドイベントです。スピードは出さず、皆で楽しく乗って、沿道の観客に笑顔で手を振ります。カラフルなドレスを着て、ハイヒールで、花で飾られた自転車に乗ります。そして、参加する女性には、ふだん自転車に乗らない友人、母親、叔母、姉妹を誘って連れてくることを奨励しています。
みんなで楽しく乗ることで、あるいは試してもらうことで、自転車の楽しさを知り、女性たちがもっと気軽に乗るようになってほしいとの願いがあるのです。特にドレスコードで制限されているわけではありませんが、みなオシャレをして自転車に乗ります。




サイクリングに不慣れな人は皆でサポートします。主催者たちは、自転車の楽しさ、喜び、娯楽としての自転車を知ってほしいと考えています。決してレースだけではなく、汗をかいて疲れるだけの移動手段ではないことを知らせたいのです。2013年に始めましたが、口コミやSNSで広がり、300人も集まりました。
翌年は参加者が2倍になり、テレビや活字メディアも取材に来ました。2015年には、イズミルだけでなく、イスタンブールやアンカラ、アダナ、エスキセヒル、マルマリス、ボドルムなどの都市にも広がりました。2016年には、数千人の女性たちが28の都市の広場を埋め尽くしました。




2017年には50都市、2018年にはトルコ以外にもイタリア、ドイツ、スイスなどの70都市に広がります。EUの運輸委員会によって国際的な女性イベントとして正式に認められました。2019年、世界の115都市に広がり、この年に世界で最も成功した草の根運動とされました。
2020年には25か国、150の都市、2021年には30か国、少なくとも150以上の都市に広がり、2022年には世界中の数百の都市で同時開催されるはずです。カーフリーデーということで環境面の共感もありますが、女性のライドイベントとしては世界有数のものとなっています。




これだけ急速に広がったのは、女性たちの連帯ということもありますが、自転車に乗る楽しさを実感した人も多かったはずです。誰でも参加できて、運営はボランティア、いかなる機関やブランドとも関係しないことも要因だと考えられます。
彼女たちは、自転車で通勤することを頼むわけではありません。クルマでなく自転車で休日に出かけるよう呼びかけるわけでもありません。ただ、この日に皆で楽しく乗るだけです。でも、それが多くの女性たちに、自転車に乗るという選択肢に気づかせ、乗ってみようかなと思わせたに違いありません。




自転車に乗る選択肢を気づかせたということは、一般的に女性は乗らないものという固定観念があったと気づかせたことでもあるでしょう。スポーツとしての自転車を、あまり魅力的と思わない人たちでも、気軽な移動手段として、気晴らしとして、楽しむために乗ってもいいことに気づいたのかも知れません。
ジェンダーフリーを声高に叫んでいるわけではありません。楽しくオシャレをして乗るだけです。でも、女性のイベントとして開催することで、多くの女性に何かの気づき、解放をもたらしたようです。少なくとも自転車の面でのジェンダーフリーに一石を投じたと言えそうです。
理化学研究所が日本人のコロナ患者の重症や死亡が、欧米に比べて非常に少ない謎の要因、「ファクターX」の一部を解明したと報じられています。本当なら日本人にとって幸運ですし、オミクロンも広がらないことを祈ります。

Amazonの自転車関連グッズ
Amazonで自転車関連のグッズを見たり注文することが出来ます。

Posted by cycleroad at 13:00│Comments(2)
この記事へのコメント
cyclaroadさん,おはようございます.
スポーツ自転車の男女格差,これは小さくない問題だと思います.約50年前,日本ではサイクリング自転車が男子小中学生に人気を集めましたが,男子のジュニアスポーツ自転車に対応する女子の小中学生向けの多段ギヤ付きスポーツ自転車はほぼ皆無でした.
これは当時の製造技術上の問題もあったと思いますが,「スポーツ自転車は女の子の乗るものではない」という,特に自転車業界の固定観念が障害になっていた可能性も,今思えば否定はできないと思います.約30年前にMTBがブームになってからはその点は幾分は良くなったと思いましたが.
主に中学校の通学自転車で多段ギヤ装備のスポーツタイプを禁止する学校が見られるのは,同じ距離や高低差で男子用と女子用との自転車の格差を好ましくないとした考えもあったものと想像されます.
女性向けにもきめの細かなスポーツ自転車の講習会が各地で開かれるのが望ましいでしょうね.
スポーツ自転車の男女格差,これは小さくない問題だと思います.約50年前,日本ではサイクリング自転車が男子小中学生に人気を集めましたが,男子のジュニアスポーツ自転車に対応する女子の小中学生向けの多段ギヤ付きスポーツ自転車はほぼ皆無でした.
これは当時の製造技術上の問題もあったと思いますが,「スポーツ自転車は女の子の乗るものではない」という,特に自転車業界の固定観念が障害になっていた可能性も,今思えば否定はできないと思います.約30年前にMTBがブームになってからはその点は幾分は良くなったと思いましたが.
主に中学校の通学自転車で多段ギヤ装備のスポーツタイプを禁止する学校が見られるのは,同じ距離や高低差で男子用と女子用との自転車の格差を好ましくないとした考えもあったものと想像されます.
女性向けにもきめの細かなスポーツ自転車の講習会が各地で開かれるのが望ましいでしょうね.
Posted by マイロネフ at December 11, 2021 09:10
マイロネフさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
自転車に限らず、子どものオモチャでも、男子向けはクルマとかメカとかが多く、女子向けだとままごととか、可愛いものとか、明確に指向が分かれています。
なかには、そのように与えられたオモチャに不満な子もいると思いますが、周囲もみなそうなため、自然と受け入れ、疑問に思っていない、思わなくなる面もあるのでしょう。
つまり、自転車業界に限ったことではないと思います。オモチャ業界にしても、アパレル業界にしても、誘導するつもりはなく、単に売れるものということなのかも知れません。
ジェンダーに関心が高まったおかげで、いろいろ見えてくるものがありますが、世の中には伝統的、慣習的な固定観念がいろいろあって、そのせいによるジェンダーギャップもたくさんありそうです。
自転車に限らず、子どものオモチャでも、男子向けはクルマとかメカとかが多く、女子向けだとままごととか、可愛いものとか、明確に指向が分かれています。
なかには、そのように与えられたオモチャに不満な子もいると思いますが、周囲もみなそうなため、自然と受け入れ、疑問に思っていない、思わなくなる面もあるのでしょう。
つまり、自転車業界に限ったことではないと思います。オモチャ業界にしても、アパレル業界にしても、誘導するつもりはなく、単に売れるものということなのかも知れません。
ジェンダーに関心が高まったおかげで、いろいろ見えてくるものがありますが、世の中には伝統的、慣習的な固定観念がいろいろあって、そのせいによるジェンダーギャップもたくさんありそうです。
Posted by cycleroad at December 13, 2021 13:39
※全角800字を越える場合は2回以上に分けて下さい。(書込ボタンを押す前に念のためコピーを)